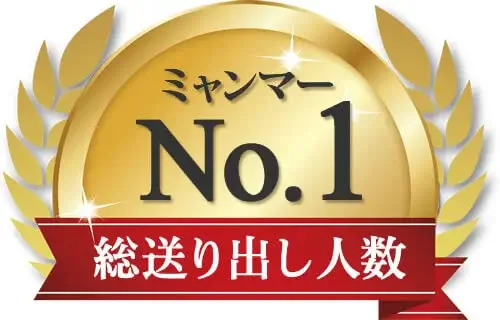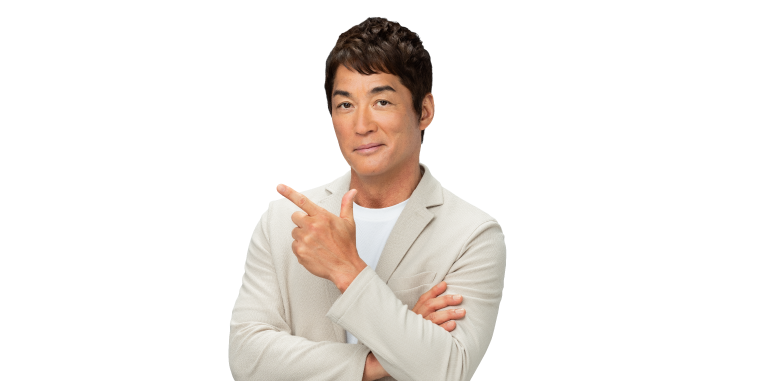特定技能2号とは?1号との違いやメリットと企業が直面する課題を解説
「即戦力となる外国人材を確保したいが、長期雇用できる人材が見つからない」――そのようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
特定技能2号は、一定の熟練した技能を持つ外国人が長期的に働ける制度であり、企業にとって安定した人材確保の選択肢となります。
さらに特定技能1号と異なり、家族帯同が可能なため、定着率の向上も期待できます。
しかし、雇用にあたってはコスト管理や転職リスクなど、注意すべき点も多くあります。
この記事では、特定技能2号の概要やメリット・デメリット、雇用時の注意点について詳しく解説しています。
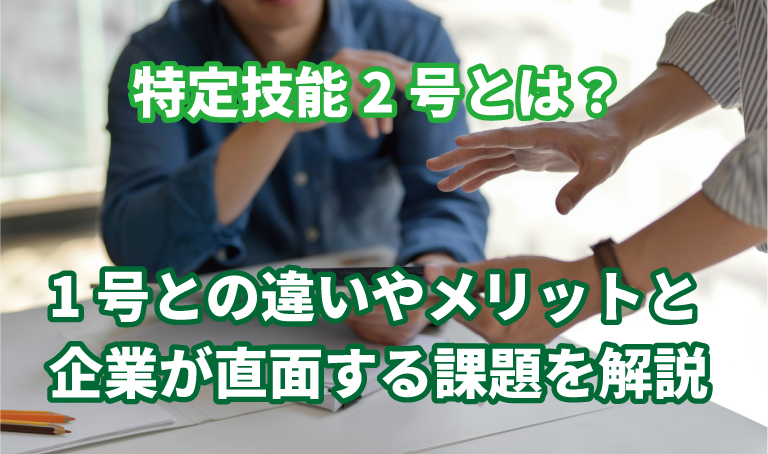
目次
特定技能2号とは?概要と特徴の基本を解説
特定技能2号の概要 - 5つのポイント
- 在留期間の上限なし: 特定技能1号とは異なり、更新を続けることで長期的な就労が可能。
- 家族の帯同が可能: 一定の要件を満たせば、配偶者や子どもと共に日本で生活できる。
- 高い技能水準が必要: 特定技能1号よりも高度な技能と経験を持つことが求められる。
- 対象分野が限定的: 2025年3月時点では外食や宿泊など11分野。今後の拡大が検討されている。
- 雇用の安定性が向上: 企業は熟練した外国人労働者を長期的に雇用できるため、人材確保の面でメリットが大きい。
特定技能2号は、日本で熟練した技能を持つ外国人労働者が長期間働けるように設計された在留資格です。
特定技能1号とは異なり、在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められるため、外国人労働者にとってより安定した生活環境が提供されます。
しかし、特定技能2号を取得するには、特定産業分野での高度な技能を証明する試験に合格する必要があります。
2025年2月現在、特定技能2号の対象となる分野は「外食や宿泊など11分野ですが、今後、他の業種にも拡大される可能性があります。
企業にとっては、特定技能2号の外国人労働者を雇用することで、長期的な戦力として活用できるメリットがあります。
特に、特定技能2号は技能レベルが高いため、即戦力としての活躍が期待できるでしょう。
特定技能2号は今後拡大されるのか?対象業種は?
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材が日本で就労するための在留資格です。
2023年6月9日の閣議決定により、対象分野が大幅に拡大されました。
これまで建設分野と造船・舶用工業分野(溶接区分のみ)に限られていた特定技能2号の対象が、新たに以下の9分野と造船・舶用工業分野の全業務区分に広がりました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
この拡大により、特定技能1号の16分野のうち、11分野で特定技能2号の受け入れが可能となりました。
なお介護分野については、既に「介護」という専門的な在留資格が存在するため、特定技能2号の対象外とされています。
特定技能2号の外国人材には、長年の実務経験などで培った熟練した技能が求められます。具体的には、自らの判断で高度な専門的業務を遂行したり、監督者として業務を統括する能力が必要とされています。
このような人材の受け入れにより、各産業分野での人手不足解消や技術力向上が期待されています。
特定技能2号を雇用する企業側のメリットとデメリットとは?
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 雇用期間 | 無期限での雇用が可能 | 長期間の雇用が前提となるため、労務管理が必要 |
| 人材確保 | 熟練技能を持つ外国人材の確保が可能 | 特定技能1号と比べると対象者が限られる |
| 家族帯同 | 家族の帯同が認められるため、定着率が向上 | 家族分の生活費負担が発生する可能性 |
| 雇用コスト | 技能レベルが高いため即戦力となる | 日本人労働者と同等以上の給与水準が求められる |
| ビザ更新 | 在留期間に制限がなく、更新手続きの負担が少ない | 入管手続きや書類管理の継続が必要 |
特定技能2号の最大のメリットは、無期限の在留が可能である点です。
特定技能1号では在留期間が最長5年に制限されておりますが、特定技能2号では更新を続けることで無期限での在留が可能となります。
また、特定技能1号では家族帯同が認められていませんが、特定技能2号では一定の要件を満たせば配偶者や子どもとともに日本で生活することが可能です。
そのため企業は長期的に熟練した外国人労働者を確保でき、人手不足の解消につながります。
さらに、特定技能2号の労働者は、特定技能1号と異なり、高度な専門知識と実務経験を持つことが前提であり、企業にとって即戦力としての活躍が期待できる点も大きなメリットと言えるでしょう。
このように、特定技能2号は、企業にとって長期的な人材確保と労働者の定着を実現しやすい制度であり、特定技能1号と比べても多くのメリットがあります。
一方で、デメリットとしては、特定技能2号の対象者が限られるため、人材の確保が難しい点が挙げられます。
また、長期間の雇用が前提となるため、企業側には安定した労務管理を行う必要があることにも注意しなければなりません。
特定技能2号を活用する際には、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、長期的な人材戦略を検討することが重要です。
この章では、特定技能2号の企業側のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
特定技能2号を雇用する企業側の5つのメリット
特定技能2号を活用することで企業が得られる利点
- 長期雇用が可能:特定技能2号は在留期間の制限がなく、安定した雇用が可能。
- 家族帯同が可能:特定の条件を満たせば、配偶者や子どもを日本に呼ぶことができる。
- 即戦力としての活躍:高度な技能を持つ外国人を採用できるため、短期間での業務習熟が可能。
- 国内人材の補完:深刻な人材不足の業界において、安定的な労働力確保が可能。
- 企業の国際化促進:外国人材の活用により、企業の多様性とグローバル展開を強化。
特定技能2号は、特定の産業分野で熟練した技能を持つ外国人を対象としており、在留期間の上限がなく、長期的な雇用が可能です。
一般的な外国人労働者の在留資格では更新手続きや滞在期限の制約があるため、企業は人材の入れ替えや新規採用に多くのコストと時間を費やさなければなりません。
しかし、特定技能2号の導入により、企業は長期的な人材戦略を立てやすくなります。
さて、そんな特定技能2号のメリットを最大限に活かすには、どうしたら良いのでしょうか?
特定技能2号のメリットを最大限に活かす企業側の工夫
企業側は、外国人労働者が日本で働き続けるための環境整備が求められます。
特に、キャリアアップの機会を提供することが、特定技能2号の外国人材の定着に不可欠です。
昇進やスキルアップの制度を整えることで、働く意欲を高め、企業に対する帰属意識を強化できます。
例えば、資格取得支援制度を導入し、さらなる専門性を高める機会を提供することで、より長期的に働く意欲を引き出すことができるでしょう。
また、特定技能2号の転職や帰郷を防ぐためには、社内環境の整備も欠かせません。
外国人労働者が働きやすい職場を作るために、外国語での労働条件の明確化や、公正な評価制度を導入することが重要です。
もちろん日本人従業員との良好な関係を築けるよう、異文化理解の研修を実施し、チームワークの強化を図ることも有効でしょう。
このように、特定技能2号の外国人材を活用するには、単なる労働力としてではなく、企業の成長を支える貴重な人材として育成する意識が重要です。
キャリア形成支援や職場環境の整備を通じて、安定的な人材確保を実現し、業務効率の向上にもつなげることができるでしょう。
特定技能2号の雇用時に注意したいデメリットとリスク
特定技能2号の雇用時に注意したいデメリットとリスク
- 人件費の増加:特定技能2号の外国人は高度な技能を持つため、給与水準が高くなりがち。
- 転職リスクの増加:在留期間に制限がなく、より条件の良い職場へ転職する可能性もでてくる。
- 家族帯同による負担:配偶者や子どもを帯同できるため、生活支援や福利厚生の負担が増える可能性がある。
- 文化・言語の壁による適応の難しさ:日本語能力や職場文化への適応に時間がかかることがある。
- 法改正による影響:入管法や労働法の変更により、雇用ルールが変わる可能性がある。
特定技能2号の外国人労働者は、特定技能1号と比較して高度な技術を持つため、給与水準が高くなる傾向があるためコストがかかります。
また社会保険や福利厚生の負担も増加し、企業の総人件費に大きな影響を与えます。
特に、地方の中小企業にとっては、これが財務面の負担となるケースが少なくありません。
ただ、だからといって給与水準を上げすぎると既存の日本人従業員との賃金バランスが崩れ、不満が生じるリスクがあります。
意外に見落とされがちな既存の従業員との給与ギャップ
特定技能2号を雇用する際には、新卒社員とのギャップを考慮した給与設計が重要です。
例えば、現在の日本では人手不足が深刻化する中、新卒採用時に給与を引き上げる動きが広がっています。
企業によっては、即戦力となる人材を確保するために初任給を大幅に引き上げていますが、これによって既存の社員との賃金差が生じ、不満につながるケースが見られています。
同様に、特定技能2号の外国人労働者の給与を市場相場に合わせて設定する際も、既存の従業員とのバランスを考慮し、段階的な給与改定やキャリアアップの仕組みを整えることが必要不可欠です。
具体的には、新卒社員と同様に、特定技能2号の労働者に対しても、入社後のスキル習得に応じた昇給制度や、日本人社員と共通の評価基準を設けることで公平感を保つことが求められます。
このように、企業が適正な給与体系を整備し、社内の給与ギャップを防ぐ取り組みを進めることが、特定技能2号の活用を成功させるカギとなるでしょう。
特定技能2号の人件費対策と注意点:コスト増加を抑える方法
特定技能2号を雇用する際には事前に人件費シミュレーションを行い、適正な給与設定を検討することが非常に重要です。
特定技能2号の外国人労働者は、高度な技能を持つため給与水準が高くなりがちですが、適切な計画なしに雇用を進めると、企業の財務負担が大きくなり経営を圧迫する可能性があります。
注意点としては、以下の点が挙げられます。
- 業界相場と賃金バランスの考慮:特定技能2号のみを優遇せず、公平な評価制度を導入。
- 段階的な昇給制度の整備:スキル評価に基づく昇給で、企業の負担を分散。
- キャリアアップ支援:研修や資格取得制度を整備し、長期定着を促進。
- 助成金・補助金の活用:自治体や業界団体の支援制度を事前に確認し、活用。
- 計画的な人事戦略の構築:給与設計、公平性確保、育成計画を総合的に実施。
まず、先にも触れたように給与設定の際には、業界の相場や既存従業員の賃金バランスを考慮することが不可欠です。
次に特定技能2号の外国人を育成しながら昇給制度を導入することで、段階的なコスト調整が可能になります。
例えば、一定期間ごとのスキル評価を行い、それに応じて昇給する仕組みを導入することで、企業の負担を一度に増やさずに済みます。
さらに、キャリアアップの機会を設けることで、転職を防ぎ、長期的な定着につなげることができます。
加えて、政府の助成金制度や補助金を活用することも有効な手段です。
特定技能外国人の雇用に関する助成制度は、自治体や業界団体ごとに異なるため、事前に最新情報を確認し、活用できる制度を把握しておくことをおすすめします。
このように、計画的な人事戦略を持つことで、特定技能2号のメリットを活かしながら、コスト増加のリスクを抑えることが可能です。
適正な給与設計、社内の公平性確保、育成計画の策定、助成金の活用など、総合的な視点で雇用戦略を構築することが成功のカギとなります。
特定技能2号の対象者と取得条件一覧
| 項目 | 取得条件 |
|---|---|
| 対象分野 | 建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 技能レベル | 各分野で高度な技術・経験を持ち、専門的な業務を遂行できること |
| 実務経験 | 職種ごとに必要な実務経験は異なる |
| 試験要件 | 特定技能2号の試験に合格すること(各業界の基準に準ずる) |
| 家族の帯同 | 配偶者・子どもの帯同が可能 |
| 在留期間 | 更新を続けることで、在留期間の制限なし |
特定技能2号は、2023年の制度拡大により、従来の「建設」「造船・舶用工業」に加えて、農業、漁業、宿泊業、外食業などを含む11分野が対象となりました。
さて、特定技能2号取得には、特定技能1号で5年以上の実務経験を積み、特定技能2号の試験に合格することが求められます。
これは、2号が特定技能1号よりも高度な専門性を持つことを前提としているためです。
企業が特定技能2号の人材を受け入れる際には、試験対策のサポートや、長期的なキャリアプランの設計が重要です。
この章では、特定技能2号の対象者と取得条件について詳しく解説します。
特定技能2号の対象者とは?対象者の主な条件
- 特定産業分野で熟練した技能を持つこと:特定技能1号よりも高度な技術や専門知識が求められる。
- 特定技能1号での5年以上の実務経験:基本的に特定技能1号の経験を積んだ人が対象となる。
- 技能評価試験の合格が必要:各分野で設定された試験に合格し、一定の技術レベルを証明することが求められる。
- 家族の帯同が可能:特定技能1号とは異なり、条件を満たせば配偶者や子どもと一緒に日本で生活できる。
- 在留期間の制限なし:特定技能2号は更新を続けることで、実質的に無期限での在留が可能。
特定技能2号は、特定の産業分野において高度な技術を持ち、即戦力として働ける外国人労働者を対象としています。
特定技能2号は特定技能1号よりもさらに熟練した技能が求められ、各分野で設定された技能評価試験に合格することが必須です。
また、特定技能1号では最長5年間しか働けませんが、特定技能2号は在留期間の上限がなく、更新を続けることで長期就労が可能です。
そのため、安定した雇用を望む外国人労働者にとって特定技能2号は魅力的な選択肢となります。
さらに、特定技能2号では配偶者や子どもの帯同が認められるため、家族と共に日本で生活することが可能です。
これにより外国人労働者の定着率が向上し、企業にとっても長期的な雇用の安定につながります。
特定技能2号の技能試験とは?どのような試験があるのか?
| 分野 | 試験名称 | 難易度 |
|---|---|---|
| 建設 | 建設分野特定技能2号試験(電気通信・配管・塗装など) | 高い(高度な実務経験が必要) |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接・鉄工・仕上げなど) | 高い(熟練技能が必須) |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能2号試験 | 中~高(2級自動車整備士レベル) |
| 農業 | 農業技能測定試験(耕種農業・畜産農業) | 中(3年以上の実務経験が望ましい) |
| 漁業 | 漁業技能測定試験(漁船漁業・養殖業) | 高い(操船技術・漁業経験が必要) |
特定技能2号の取得には、各分野の技能試験に合格することが必須です。
上記の表で紹介している試験では業務遂行に必要な高度な技術や経験が求められており、特定技能1号と比較して、2号ではより専門的かつ管理業務の能力も問われるようになっています。
また特定技能2号の試験は、業界ごとの高度な知識と実務経験を持つ人材が対象です。
例えば、建設分野では電気通信・配管・塗装などの専門的な試験が実施され、造船・舶用工業では、溶接・鉄工・仕上げなどの分野で試験が行われます。
特定技能2号を取得するには、業務経験を積ませることが重要です。
現時点での特定技能2号の必要な実務経験と日本語要件は以下の図をご参照ください。
| 分野 | 主な職種 | 必要な試験・資格 |
|---|---|---|
| 介護 | 介護業務全般 | 介護技能評価試験、介護日本語評価試験 |
| ビルクリーニング | 建物内外の清掃業務 | ビルクリーニング分野特定技能評価試験 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 鋳造、鍛造、金属プレス加工など | 各職種ごとの特定技能評価試験 |
| 建設 | とび、型枠施工、鉄筋施工など | 建設分野特定技能評価試験 |
| 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工など | 造船・舶用工業分野特定技能評価試験 |
| 自動車整備 | 自動車の点検・修理 | 自動車整備分野特定技能評価試験 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 | 航空分野特定技能評価試験 |
| 宿泊 | ホテルのフロント、接客、清掃 | 宿泊分野特定技能評価試験 |
| 農業 | 耕種農業(野菜・果樹)、畜産農業 | 農業分野特定技能評価試験 |
| 漁業 | 漁業全般、養殖業 | 漁業分野特定技能評価試験 |
| 飲食料品製造業 | 食品加工、調理 | 飲食料品製造業分野特定技能評価試験 |
| 外食業 | レストランでの調理・接客 | 外食業分野特定技能評価試験 |
| 林業 | 森林管理、木材生産 | 林業分野特定技能評価試験 |
| 木材産業 | 製材、合板・建材製造 | 木材産業分野特定技能評価試験 |
| 自動車運送業 | トラック・タクシー・バス運転 | 自動車運送業分野特定技能評価試験 |
| 鉄道 | 駅務、保守、運転補助 | 鉄道分野特定技能評価試験 |
特定技能2号:2分野の職種一覧表
| 分野 | 主な職種 | 必要な試験・資格 |
|---|---|---|
| 外食 | 飲食物調理、接客、店舗管理など | 特定技能2号外食建設技能試験 |
| 宿泊 | フロント、企画・広報、接客など | 特定技能2号宿泊技能試験 |
多くの試験では、試験対策講座や模擬試験が用意されており、企業側も外国人労働者が合格できるよう、試験対策のサポートを積極的に行うことが求められます。
特定技能2号の在留期間と家族帯同の条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 在留期間 | 3年、1年、または6ヵ月ごとの更新(更新を続ければ無期限での在留が可能) |
| 家族帯同 | 要件を満たせば配偶者・子どもの帯同が可能 |
| 技能要件 | 特定技能2号の試験合格または相当する技能の証明 |
| 雇用契約 | 安定した雇用が確保され、日本人と同等以上の待遇があること |
| 支援義務 | 特定技能1号とは異なり、企業側に支援義務はなし |
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が長期的に日本で働くことを目的とした制度のため在留期間の上限がなく、更新を続けることで無期限の在留が可能となります。特定技能1号では家族の帯同が認められていませんが、特定技能2号では一定の条件を満たせば、配偶者や子どもを帯同できるようになります。
また特定技能2号の労働者を受け入れる企業には、特定技能1号とは異なり、支援義務が課されません。
しかし、企業は特定技能2号の外国人に対して、安定した雇用と日本人と同等以上の待遇を保証する必要があります。
特に給与や労働環境については、日本人と同等またはそれ以上の条件を確保しなければなりません。
特定技能2号の在留資格と在留期間の更新手続きについて
特定技能2号の在留資格は、
3年、1年、または6ヵ月ごとの更新となります。
ただし、更新を継続すれば長期的な在留が可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請対象者 |
・特定技能2号の在留資格を持つ外国人労働者 ・継続して同一企業または業界で就労している者 |
| 更新のための主な審査項目 |
・技能の維持・向上:分野ごとの技能評価試験に合格し、一定の技術水準を維持していること ・雇用契約の安定性:企業との契約が継続しており、適正な労働条件が確保されていること ・生活基盤の安定:収入が安定しており、日本での生活が継続可能であること |
| 申請の流れ |
1. 必要書類の準備(雇用契約書、在職証明書、給与明細、技能評価試験の合格証明など) 2. 地方出入国在留管理局への申請(企業または本人が提出) 3. 審査・承認(要件を満たせば更新許可が下り、新しい在留カードが発行される) |
| 更新手続きでの注意点 |
・企業側の義務:給与が日本人と同等以上であることを証明し、適切な労働環境を提供する必要がある ・不正雇用のリスク:違法な労働環境を提供した場合、在留資格の更新が拒否され、企業にもペナルティが科される可能性がある |
| 特定技能1号との違い | ・特定技能1号は在留期間の上限が5年だが、特定技能2号は更新を続けることで無期限の在留が可能 |
特定技能2号の更新手続きは、企業と外国人労働者双方が計画的に準備を進めることが不可欠です。
特に、安定した雇用関係の維持と技能レベルの証明が重要なポイント となります。
企業は、外国人労働者が日本で長期的に働けるよう、適正な労働条件を提供し、必要な技能評価試験の受験を支援することが求められます。
また在留資格の更新には、雇用契約の継続や給与水準の適正性が審査対象となります。
そのため、企業は労働環境の整備を怠らず、労働者が安心して働ける環境を維持することが必要不可欠です。
特定技能2号の家族帯同の条件と申請手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家族帯同の対象 | 配偶者および子に限られる |
| 帯同が認められる条件 |
・特定技能2号の在留資格を持っていること ・安定した収入があり、日本での生活維持が可能であること ・雇用契約が継続しており、適正な労働条件が確保されていること |
| 申請に必要な書類 |
・家族関係を証明する書類(戸籍謄本、結婚証明書など) ・在職証明書および収入証明書 ・住宅確保の証明(賃貸契約書など) |
| 申請の流れ |
1. 必要書類の準備 2. 地方出入国在留管理局への申請 3. 審査・承認(要件を満たせば帯同許可が下りる) |
| 企業側の責任 | 外国人労働者が安定した生活を送れるようサポートを行う |
特定技能2号では、上記の表のように一定の条件を満たせば配偶者や子の帯同が認められます。
ただし、両親や兄弟姉妹は対象外です。
家族帯同の可否は、外国人労働者の雇用の安定性や収入状況 によって決まります。
申請時には、家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)や、安定した生活基盤があることを示す書類(在職証明書、給与明細、住居契約書)が必要になります。
また企業側も、労働者が安定した生活を維持できる環境を提供することが求められます。
特定技能2号の家族帯同の申請手続きは地方出入国在留管理局で行われ、審査の結果によって帯同が許可されます。
特定技能2号から永住権を取得する方法と条件
理解しておくべき4つのポイント
- 永住権取得の基本条件:原則として、日本に引き続き10年以上在留していることが必要(特定技能2号はこれに該当)。この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 安定した収入:一定の年収水準を満たし、長期的に安定した生活を維持できること。
- 技能実習・特定技能1号の期間のカウント:技能実習や特定技能1号での滞在期間は、基本的に10年要件には含まれない。
- 社会的信用:納税・社会保険の適正な支払い、犯罪歴がないことなどが求められる。
特定技能2号は在留期間の制限なく 日本で働き続けることができる制度であり、日本での永住権の取得を目指す外国人にとって、有利な在留資格の一つとされています。
永住権を申請するには、日本で10年以上継続して在留していることが基本条件です。
ただし、特定技能1号や技能実習の期間はカウントされないため、特定技能2号としての在留期間だけがカウントされます。
また、安定した収入を得ており、年収の目安は300万円以上とされることが多いです。
家族帯同の場合はさらに高い水準が求められます。
さらに日本で特定技能2号として働いている間に税金や社会保険を適正に支払い、交通違反や犯罪歴がないことも審査の対象となります。
特に、飲酒運転などの重大な違反歴があると、永住申請は厳しくなります。
そして、特定技能2号の永住権獲得の流れは次のようになっています。
永住許可申請の流れ
- 必要書類の準備(在職証明書、収入証明、納税証明など)
- 地方出入国在留管理局への申請
- 法務省の審査(数か月〜1年程度)
- 承認後、永住者としての在留カード発行
在職証明書や収入証明、納税証明などの必要書類を準備し、地方出入国在留管理局へ申請します。
その後、法務省による審査が行われ、数か月から1年程度の期間を経て永住許可が承認され、承認後に新しい在留カードが発行されることで正式に永住者として認められる流れになっています。
永住権取得までの詳しい流れについては以下の記事もご参考ください。
特定技能2号のまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能2号の特徴:高度な技能を持ち、在留期間の上限なし・家族帯同が可能。
- コスト増加のリスク:給与水準が高く、社会保険や福利厚生の負担が増加する。
- 転職のリスク:在留期間に制限がないため、より良い条件の企業に転職しやすい。
- 公平な給与制度の重要性:日本人社員との給与バランスを考慮し、評価基準を明確にする。
- 適切な人材確保の必要性:信頼できる送り出し機関と連携し、優秀な外国人材を確保する。
この記事では、特定技能2号の特徴、リスク、雇用時の注意点について解説しました。
特定技能2号の活用は、人手不足の解決策として有効ですが、コスト管理や転職リスクへの対策が欠かせません。
特に、公平な給与制度を整え、長期的な定着を促進する仕組みが必要です。
すぐれた外国人材を確保するには、信頼できる送り出し機関のサポートを受けることが成功の鍵となります。
ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」は、候補者の選定から入国手続き、定着支援まで一貫したサポートを提供し、企業がスムーズに特定技能2号人材を活用できるよう支援しています。
▶ ミャンマー・ユニティへのお問い合わせはこちら
▶ミャンマー・ユニティ公式サイト無料でご提供しております