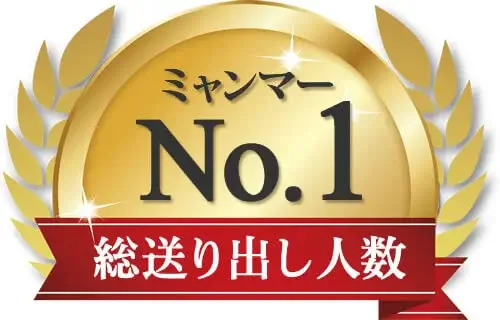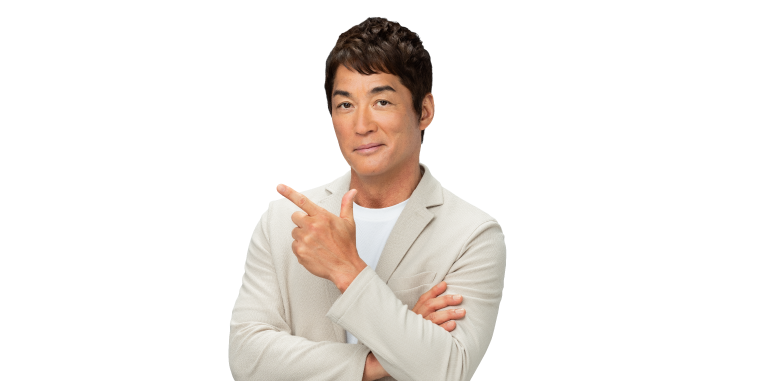特定技能「自動車運送業」で即戦力を確保!受け入れ企業のメリットと必要な準備とは?
日本の自動車運送業界では、ドライバー不足が深刻化し、物流の停滞やサービスの質の低下が懸念されています。
特に、2024年問題による労働時間の制限が加わり、人材確保が企業経営の大きな課題となっています。
しかし、日本国内でのドライバーの採用が難しい中、特定技能制度を活用し、外国人材を採用する企業が増えているのをご存じでしょうか?
この制度を適切に活用すれば、即戦力となる人材を確保し、長期的に安定した事業運営が可能になります。
ただ、特定技能外国人の受け入れの条件や手続きが分からず、導入に踏み切れない企業も多いでしょう。
この記事では、特定技能「自動車運送業」の概要や試験内容、受け入れ要件について詳しく解説しています。
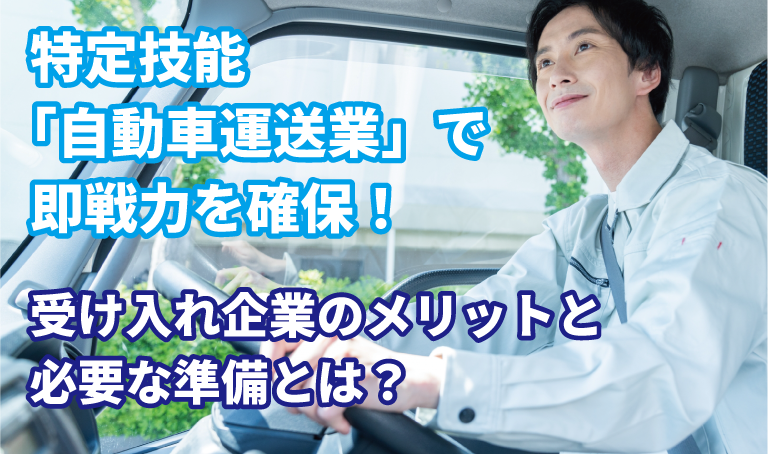
目次
特定技能自動車運送業とは?受け入れが開始された背景
特定技能自動車運送業の概要
- 特定技能制度:日本の人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と専門性を持つ外国人材を受け入れるための在留資格制度です。
- 自動車運送業の追加:2024年3月、新たに「自動車運送業」が特定技能の対象分野に加えられました。
- 受け入れ見込み数:今後5年間で最大24,500人の外国人労働者の受け入れが予定されています。
- 受け入れ企業の要件:労働・社会保険・租税に関する法令の遵守に加え、トラックドライバーの上乗せ要件として「働きやすい職場認証の取得」あるいは「安全性優良事業所(Gマーク)の保有」が求められています。タクシードライバー・バスドライバーの上乗せ要件として「道路旅客運送業であること」「新任運転者研修の実施」が求められます。
- 外国人ドライバーの役割:即戦力として、日本の自動車運送業を支える重要な人材として期待されています。
日本の物流・旅客輸送業界は、少子高齢化や労働環境の厳しさから、長年にわたりドライバー不足に直面してきました。
特にトラックドライバーにおいては、2024年4月から施行された「働き方改革関連法」により、時間外労働が年間960時間に制限されることとなりました。
これにより、従来の長時間労働に依存していた輸送体制の維持が困難となり、さらなる人手不足が懸念されています。
国土交通省の試算では、2024年には営業用トラックの輸送能力が14.2%不足し、対策が講じられない場合、2030年には34.1%の不足が予測されています。
これらの課題に対応するため、政府は特定技能制度に「自動車運送業」を追加し、外国人労働者の受け入れを推進することとしました。
この制度によって即戦力となる人材を確保し、物流・旅客輸送業界の持続可能性を高めることが期待されています。
ドライバー不足の現状と労働市場への影響
- 年齢構成の偏り:トラック業界の40~54歳の割合は約45.2%、29歳以下は10%以下。
- 女性の就業率の低さ:女性トラックドライバーの割合はわずか2.5%と全産業平均を大きく下回る。
- 働き方改革の影響:時間外労働の制限で輸送能力の維持が困難に。人手不足がさらに深刻化。
- 倒産リスクの増加:2024年のタクシー業倒産・廃業件数は82件、主因の40%以上が人手不足。
- 自動化への期待:政府は東京-大阪間に自動貨物輸送回廊を計画。2030年代半ばに本格稼働予定。
日本の自動車運送業界は、深刻なドライバー不足に直面しています。
国土交通省のデータによれば、トラック業界の就業者の約45.2%が40~54歳であり、29歳以下の若年層は全体の10%以下にとどまっています。
さらに、女性の就業者割合は2.5%と、全産業平均と比較して極めて低い状況です。
このような年齢構成の偏りと若年層の減少は、将来的な労働力不足を一層深刻化させる要因となっています。
特に、2024年に施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されました。
その結果として従来の長時間労働に依存していた輸送体制の維持が困難となり、さらなる人手不足が懸念されています。
2024年にはタクシー業の倒産・廃業件数が82件に達し、過去最多を更新しました。
これらの倒産のうち、少なくとも40%以上がドライバー不足を主な要因としています。
また、ドライバー不足と労働時間短縮の影響で、経営者や役員自らがドライバー業務を担うケースも増加しており、労働力不足が企業経営に直接的な悪影響をもたらしていることを示しています。
自動車運送業の特定技能追加の経緯は?いつから始まる?
- 2024年3月29日:政府は特定技能制度の対象分野に自動車運送業を含めることを閣議決定。
- 2024年4月19日:具体的な制度の方針と運用要領が公表され、業界内での準備が進む。
- 2024年12月19日:上乗せ基準告示が施行され、自動車運送業分野での特定技能外国人の受け入れが正式に開始。
- 2025年1月17日:自動車運送業分野の協議会が発足し、受け入れ体制の整備が進む。
- 2025年春:特定技能外国人トラックドライバーの第1号認定者が埼玉県で就労を開始する予定。
日本の自動車運送業界は深刻な人手不足に直面しており、政府はこの課題に対応するため、特定技能制度の対象分野に自動車運送業を追加することを決定しました。
2024年3月29日、政府は自動車運送業を含む4分野を新たに特定技能制度の対象とすることを閣議決定。
その後、2024年4月19日に具体的な制度の方針と運用要領が公表され、業界内での準備が本格化しました。
さらに、2024年12月19日に上乗せ基準告示が施行され、自動車運送業分野での特定技能外国人の受け入れが正式に開始されました。
これに伴い、2025年1月17日には自動車運送業分野の協議会が発足し、受け入れ体制の整備が進められています。
さらに、2025年春には特定技能外国人トラックドライバーの第1号認定者が埼玉県で就労を開始する予定です。
特定技能:「自動車運送業」の制度について詳しく知ろう!
特定技能「自動車運送業」の概要
- 制度の目的:深刻なドライバー不足を補い、物流・旅客輸送を安定させるために導入された。
- 対象業務:トラック輸送(宅配・長距離・引越し)、タクシー・バス運転、物流センター業務など。
- 必要な資格:運転業務では日本の免許(母国で免許を取得した人は外免切り替えまたは免許取得が必要)が必要。一定の日本語能力も求められる。
- 雇用企業の義務:労働環境の整備、生活支援、研修の実施が義務付けられている。
- 制度のメリット:外国人材の活用で人手不足を解消し、安定した運送サービスの提供が可能。
特定技能「自動車運送業」は、日本の物流・旅客輸送業界の人手不足を解消するために導入された制度です。
職種としてはトラックドライバー、タクシー運転手、バス運転手が対象となっています。
この制度を利用する外国人は、運転スキルと日本語能力の両方で一定の基準を満たす必要があります。
特定技能「自動車運送業」の受け入れ要件と企業が満たすべき条件
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 受け入れ対象業種 | 道路旅客運送業(バス・タクシー)および道路貨物運送業(トラック) |
| [トラックドライバー上乗せ要件] 認証制度の取得 |
「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク(安全性優良事業所)」の取得 |
| 特定技能協議会への参加 | 国土交通省が設置する特定技能協議会の構成員となる必要がある |
| [タクシードライバー・バスドライバー上乗せ要件] 新任運転者研修の実施 |
特定技能外国人の受け入れ企業は、新任運転者研修の実施が義務付けられる |
| 労働条件の確保 | 日本人と同等以上の報酬を保証し、適正な労働環境を整備する |
特定技能「自動車運送業」は、日本国内のドライバー不足を補うために創設された制度です。
外国人ドライバーを適切に受け入れるためには、企業が上記の不要の要件を満たしている必要があります。
まず、受け入れ企業は、道路旅客運送業(バス・タクシー)または道路貨物運送業(トラック)を営む事業者であることが必須です。
また「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク(安全性優良事業所)」を取得をするために、労働環境の改善も求められます。
国土交通省が設置する特定技能協議会への参加が義務付けられており、外国人労働者の適切な受け入れと支援を行う体制を整えなければなりません。
さらにタクシードライバーとバスドライバーは新任運転者研修の実施も義務となっており、特定技能外国人が日本の交通ルールや業務内容を正しく理解し、安全に業務を遂行できるようにすることも企業側に求められています。
そして、労働条件についても厳格な基準があり、特定技能外国人には日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
外国人労働者であっても日本人と同じ給与を支払う必要があります。
企業がこれらの要件を満たすことで、特定技能外国人を適切に受け入れることが可能となります。
特定技能制度の活用を検討している企業は、まずこれらの条件を整備し、計画的な受け入れ体制を構築することが重要です。
特定技能外国人の運転免許の取得ルール
- 国内免許の取得必須:日本で運転するには、特定技能外国人も日本の運転免許を取得する必要がある。
- 外免切替試験の受験:運転免許を取得する方法として、母国で免許を取得している方は外免切替にて免許を取得することもできる。
- 求められる免許の種類:トラックは運転する車のサイズにより普通または準中型または中型または大型免許が必要、タクシー・バスは第二種運転免許が必要。
- 免許取得の所要期間:普通・準中型免許は最短2週間、大型免許や二種免許は数カ月かかることもある。
- 語学要件の影響:試験や講習の理解が必須なため、できるだけ高い日本語能力が推奨される。
特定技能外国人が日本の運送業で働くには、業務内容に応じた運転免許の取得が必須です。
例えば、トラックドライバーは運転する車のサイズにより普通または準中型または中型または大型免許が必要、タクシーやバスの運転には第二種運転免許が求められます。
特定技能外国人が母国で運転経験がある場合でも、日本の交通ルールに適応するため、日本国内での運転免許の取得や外免切替試験を受ける必要があります。
特に、大型車両の運転には高度な技術が求められるため、免許取得までに数カ月かかることもあります。
そのため、企業は外国人ドライバーを採用する際に、免許取得の計画や運転免許取得のためのサポート体制を整える必要があります。
特定技能「自動車運送業」で求められる日本語レベル
- 最低限の基準:トラックは日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)、タクシー・バスは日本語能力試験N3以上合格が求められる。
- 業務上の会話:運行管理者や荷受け担当者との連絡を正確に行う必要がある。
- 標識や書類の理解:道路標識や運行指示書を正しく読み取る力が必要。
- 緊急時の対応:事故やトラブル発生時に適切な報告や指示の理解が求められる。
- 研修の必要性:業務に即した日本語研修を行い、実務での会話力を高めることが重要。
特定技能「自動車運送業」で働くには、日常会話レベル以上の日本語能力が必要です。
特にトラックやタクシー業務では、荷受け担当者とのやり取りや運行管理者との連絡が欠かせないため、日常会話レベル以上の日本語能力がないと働くのは難しくなってしまうでしょう。
また、業務上では道路標識の理解や運行指示書の読み取りが求められるため、単に話せるだけでなく、正確な読解力も求められます。
そのため特定技能外国人を受け入れる企業側は、特定技能外国人がスムーズに業務を遂行できるよう、業務に即した日本語研修を実施し、実務レベルの会話力を高めるサポートする必要があります。
その理由は、運送業務において円滑なコミュニケーションが欠かせないからです。
例えば、運行管理者や荷受け担当者との連携が必要となる場面では、正確な指示の理解と適切な返答が求められますし、配送先での荷受け時の確認作業や、トラブル発生時の適切な報告・対応もできるようになっていないと業務に支障が出てしまいます。
また標識や運行指示書の誤読は、事故や業務遅延につながるリスクがあるため、研修を通じて必要な語学力を習得させることが不可欠です。
だからこそ特定技能外国人を企業が雇用する際には、適切な研修を実施し、正しくサポートすることが大切なのです。
特定技能: 自動車運送業の対象職種と業務内容一覧
| 対象職種 | 業務内容 |
|---|---|
| トラックドライバー | 貨物輸送(一般貨物・引越し・宅配便など)、安全運行管理、車両点検 |
| タクシードライバー | 旅客輸送、接客業務、運賃精算、ナビゲーション業務 |
| バスドライバー | 路線バス・観光バスの運行、安全運転管理、乗客対応 |
特定技能の自動車運送業分野では、主に貨物輸送や旅客輸送に関わる職種が対象となります。
また、長距離・中距離トラックドライバーや宅配ドライバーだけでなく、タクシードライバーやバスドライバーも特定技能の対象となっています。
さらに、物流センター業務や運行管理者補助といった間接業務も行えるようになりました。
このように特定技能制度を活用することで、物流業界や旅客輸送業界の人手不足を補い、安定した輸送ネットワークの維持が可能になるでしょう。
特に、ドライバー不足や業務の負担増に悩む運送会社やタクシー・バス事業者が、適切な人材配置と研修体制の整備を進めることで、即戦力となる外国人材を活用でき、業務の効率化と安全性の向上が期待できます。
この章では、自動車運送業の対象職種と業務内容について詳しく解説します。
トラックドライバー:物流の最前線を支える即戦力
特定技能外国人ができる業務・メリット・注意点
- できる業務:一般貨物輸送、宅配便、引越し業務、積み降ろし作業、車両点検、安全運行管理。
- 導入メリット:慢性的なドライバー不足の解消、宅配・長距離輸送の安定化、採用コストの削減。
- 注意点:大型・特殊車両の運転には日本の免許が必須。事故防止のため安全教育を徹底する必要あり。
日本の物流は、EC市場の拡大や人手不足の影響で深刻なドライバー不足に直面しています。
とくに、宅配便や長距離輸送は労働負担が大きく、国内の若年層の就業希望者が減少。
結果として、企業は採用難に陥り、配送の遅延やコスト増加が避けられない状況です。
特定技能外国人は、これらの課題解決に貢献します。
特に、準中型免許を取得することで宅配や一般貨物輸送が可能になり、さらに経験を積めば、大型免許を取得して長距離輸送にも対応できます。
ただし、言語の壁によるコミュニケーション不足が安全管理の課題となるため、企業は運行管理体制の強化や、研修を通じた安全教育の徹底が不可欠です。
タクシードライバー:都市交通と観光需要に対応する人材
特定技能外国人ができる業務・メリット・注意点
- できる業務:旅客輸送、接客業務、運賃精算、ナビゲーション、インバウンド対応。
- 導入メリット:都市部のドライバー不足解消、訪日外国人観光客の対応強化、新たな収益源の確保。
- 注意点:日本語での接客スキル必須。地域によっては地理試験の合格が必要。
都市部のタクシー業界では、ドライバーの高齢化により人材不足が深刻化しています。
特に、観光需要が回復しつつあるなか、訪日外国人の移動手段としてタクシーの役割はますます重要になっています。
特定技能外国人は、一定の日本語能力を備えたうえで、観光客向けのサービス強化にも貢献してくれることでしょう。
例えば、多言語対応が可能なドライバーを増やすことで、外国人観光客の利便性向上につながり、新たな市場開拓にも期待できます。
ただし、タクシーの接客業務では高い日本語スキルが求められ、運賃精算や道案内の正確性が必要です。
また、地域によってはタクシー乗務に必要な地理試験があり、外国人採用時のハードルとなるケースもあるため、外国人労働者に対するサポート体制の構築が重要になります。
バスドライバー:公共交通の維持と観光業の発展に貢献
特定技能外国人ができる業務・メリット・注意点
- できる業務:路線バス・観光バスの運行、乗客対応、安全運行管理、緊急時対応。
- 導入メリット:地方の公共交通維持、観光需要への対応強化、ドライバー不足の長期的解消。
- 注意点:大型二種免許が必須。緊急時の対応や安全管理に関する研修が不可欠。
日本の公共交通は、都市部だけでなく地方の移動手段としても不可欠ですが、ドライバー不足のため、一部地域では減便や路線廃止が相次いでいます。
特に、観光地では訪日客の増加により、バスドライバーの確保が急務となっています。
特定技能外国人を活用すれば、地方の公共交通を維持しながら、観光バス業界の発展にもつなげることを目指せるでしょう。
ただし、特定技能外国人がバスドライバーとして働くには、大型二種免許の取得が必須であり、乗客対応や緊急時の行動指針を習得する必要があります。
また、外国人乗務員が増えることで、乗客の安全性への不安を払拭するための対応も求められるため、企業側は丁寧な教育やトレーニングの実施が不可欠です。
特定技能「自動車運送業」の試験概要
特定技能「自動車運送業」分野で働くためには、以下の試験に合格する必要があります。
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験:学科試験と実技試験があり、運行業務や安全衛生に関する知識と技能が問われます。
- 日本語能力試験:トラック運転手の場合、日常会話が可能な日本語能力(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストで200点以上(JFT Basic A2レベル)、タクシー・バスは日本語能力試験N3以上の合格が必要です。
- 運転免許の取得:トラック運転手は第一種運転免許、バス・タクシー運転手は第二種運転免許の取得が求められます。
特定技能「自動車運送業」分野での就労を目指す外国人には、上記の試験合格が必須となります。
これらの試験は、運行業務や安全衛生に関する知識と技能、そして日本語能力を評価するものです。
各試験の詳細と合格基準について、さらに詳しく紹介します。
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
- 試験構成:学科試験と実技試験の2種類で構成され、それぞれの知識と技能を評価。
- 試験内容:学科は運行業務・安全衛生の○×形式30問、実技は三肢択一20問を出題。
- 合格基準:学科・実技ともに正答率60%以上で合格とされる。
この試験は、学科試験と実技試験で構成されています。
学科試験では、運行業務や安全衛生に関する知識が問われ、○×形式の問題が30問出題されます。
また実技試験では、三肢択一形式の問題が20問出題され、実務的な技能が評価され、合格基準は、学科試験および実技試験のそれぞれで正答率60%以上とされています。
日本語能力試験
- 必要なレベル:トラック運転手は、日常会話レベルの日本語能力が求められる。
- 試験基準:日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格、または国際交流基金日本語基礎テストで200点以上の取得(JFT Basic A2レベル)が必要。
- タクシー・バス運転手:乗客対応のため、日本語能力試験(JLPT) N3以上の日本語能力が求められる。
特定技能外国人がトラック運転手を目指す場合、日常会話が可能な日本語能力が求められます。
そのため日本語能力試験(JLPT)のN4以上の合格、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で200点以上(JFT Basic A2レベル)を取得する必要があります。
一方、バスやタクシーの運転手を目指す場合、乗客とのコミュニケーションが必要となるため、より高い日本語能力(JLPT N3以上)が求められます。
タクシーでは、目的地の確認や運賃精算、観光客への対応など、乗客と的確にやり取りする日本語での会話スキルが必要不可欠です。
またバス運転手も、停留所の案内や高齢者・外国人観光客への対応、緊急時のアナウンスを行う必要があり、より高度な日本語運用能力が求められます。
そのため、企業は特定技能外国人向けに接客や業務に即した日本語研修を実施し、スムーズな運行をサポートするようにしましょう。
運転免許の取得
- 必要免許:トラック運転手は運転する車のサイズにより普通または準中型または中型または大型免許が必要、バス・タクシーは第二種免許が必要。
- 外免切替の要件:運転免許を取得する方法として、母国で免許を取得している方は外免切替にて免許を取得することもできる。
- 免許取得の所要時間:準中型は最短2週間、大型免許や二種免許は数カ月かかることもある。
日本での運転業務に従事するためには、適切な運転免許の取得が必要です。
トラック運転手の場合、第一種運転免許が必要です。
またバスやタクシーの運転手の場合、乗客を安全に輸送する責任があるため、第二種運転免許を取得しなければなりません。
これらの免許は、日本の自動車教習所での教習や、外国の免許を日本の免許に切り替える外免切替手続きを通じて取得することが可能です。
各試験の詳細や最新情報については、関連する公式ウェブサイトをご確認ください。
運転免許試験に合格し、日本国内の免許を取得することで、特定技能「自動車運送業」分野での就労が可能となります。
特定技能「自動車運送業」のまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能制度の目的:自動車運送業の深刻な人手不足を解消するため、外国人労働者を受け入れる制度。
- 必要な資格と日本語能力:運転業務には適切な運転免許が必要。トラックドライバーは、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basic 200点以上(JFT Basic A2レベル)の取得が求められる。タクシー・バスドライバーは日本語能力試験(JLPT) N3以上の取得が求められる。
- 受け入れ企業の要件:労働環境の整備、新任運転者研修の実施、特定技能協議会への参加が必須。
- 試験概要:自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格することが必要。
- 特定技能外国人の活用メリット:即戦力としての採用が可能で、物流の安定化や業務の効率化につながる。
この記事では、特定技能「自動車運送業」に関する受け入れ要件や必要な試験、企業が満たすべき条件について解説しました。
特定技能制度を活用することで、
ドライバー不足に悩む企業は即戦力となる外国人材を確保できます。
しかし、手続きの複雑さや適切な人材の選定、研修体制の構築など、課題も多くあります。
そこでおすすめなのが、ミャンマー政府認定圧倒的No.1の送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」です。
ミャンマー・ユニティは、人材の選定から渡航手続き、就労後の定着支援までを一貫してサポートし、企業の負担を軽減します。
ミャンマー・ユニティへのお問い合わせはこちら
▶ミャンマー・ユニティ公式サイト※ 実績数値提供元:MOEAA(ミャンマー送り出し機関協会:旧MOEAF)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティは2,506名で圧倒的首位。第2位の1,054名と比較して約2.4倍の差をつけています。
無料でご提供しております