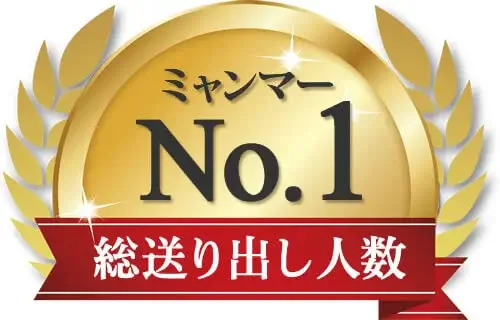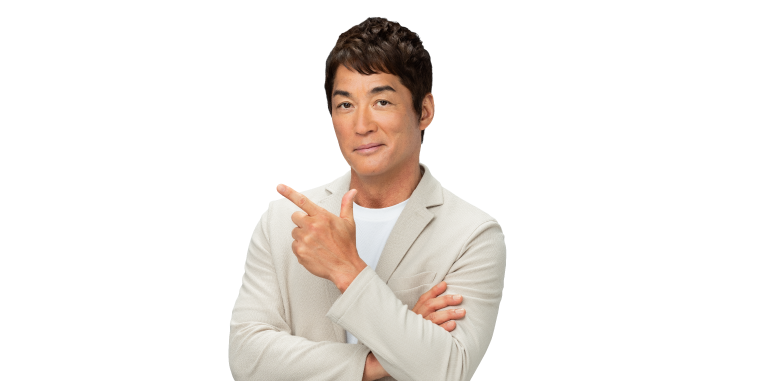特定技能外国人とは?制度の仕組みとメリットとデメリット、受け入れの流れを紹介
人手不足が深刻化する中で、特定技能外国人の受け入れを検討している企業も増えています。
しかし、「どのような制度なのか」「手続きが複雑なのでは?」と不安を感じる経営者の方も多いのではないでしょうか。
特定技能制度は、日本の労働力不足を補うために設けられた制度で、即戦力となる外国人材の雇用が可能です。
この記事では、特定技能外国人の制度概要や受け入れの流れ、注意点について詳しく解説しています。

目次
特定技能外国人とは?制度の基本概要
特定技能外国人の制度概要の5つのポイント
-
特定技能制度の目的
深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れる制度。 - 対象となる分野
介護、外食業、農業、宿泊業、自動車運送業など16の産業分野が対象。 - 在留資格の種類
「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、1号は最長5年間の在留が可能、2号は熟練技能者向けで在留期間の上限なし。 -
受け入れ要件
技能試験と日本語試験の合格が必要(技能実習2号を良好に修了した者は免除)。 -
支援体制の義務化
特定技能1号の外国人には、職場・生活支援を提供する「登録支援機関」などの支援が必須。
日本は少子高齢化の影響により、労働力不足が深刻化しています。
特に、介護・建設・外食などの業界では、日本人労働者の確保が難しく、人材不足が経営課題となっています。
この状況を打開するため、2019年に出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正によって特定技能制度が導入されました。
従来の「技能実習制度」と異なり、この制度では即戦力として働ける外国人を受け入れることを目的としています。
また、特定技能制度の導入により、企業は長期間の人材確保が可能になりました。
特定技能2号を取得すれば、在留期間の制限なく働くこともでき、家族の帯同も認められています。
しかし、特定技能外国人の受け入れには試験の合格や支援体制の整備が求められるため、導入を検討する企業は事前準備が重要です。
適切な支援機関と連携し、スムーズな雇用を進めることが、企業の成長にもつながります。
そもそも特定技能制度の目的とは?なぜこの制度が作られたのか?
日本は少子高齢化の影響で、労働力不足が深刻化しています。
総務省統計局の2022年10月1日現在のデータによれば、総人口は1億2494万7千人で、前年から55万6千人(-0.44%)減少し、12年連続で減少しています。
特に建設業界では、外国人労働者を雇用する理由として「労働力不足の解消・緩和のため」が81.3%と最も多く、全産業平均の64.8%を大きく上回っています。
このような状況を受け、政府は2019年に「特定技能制度」を導入しました。
この制度の目的は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることです。具体的には、介護、外食業、建設業、農業、宿泊業、自動車運送業など16の産業分野が対象となっています。
さらに、2024年3月には、特定技能制度の改正が閣議決定され、分野と業務内容の追加が行われました。
例えば、飲食料品製造分野では、これまで工場内での食品加工しか認められていませんでしたが、総合スーパーマーケット※や食料品スーパーマーケット※が受入れ可能な事業所として追加されました。
また、新たに自動車運送業なども特定技能の対象分野に追加されました。
この制度の背景には、国際的な人材獲得競争の激化や、従来の技能実習制度における課題が存在します。
政府は、外国人にとって魅力的な制度を構築し、日本が「選ばれる国」となることで、産業を支える人材を適切に確保することを目指しています。
※食料品製造を行うものに限る
出典②:日経ビジネス
特定技能1号と2号の違いとは?何がどう違うのか?
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象分野 | 16分野(介護、外食、宿泊、農業、建設など) | 11分野(建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空など) |
| 求められる技能 | 基本的な技能(試験合格が必要) | 熟練した技能(試験合格が必要) |
| 在留期間 | 最長5年(更新あり、延長なし) | 無期限(更新可能) |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子ども) |
| 日本語要件 | 日本語能力試験N4以上または同等レベル | 日本語試験は不要(外食と漁業はN3合格が必要) |
特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、この2つの最大の違いは、求められる技能レベルと在留期間の制限にあります。
特定技能1号は、基本的な技能を持つ外国人が対象で、試験に合格することで16の産業分野(介護、外食、宿泊、農業、自動車運送業、建設など)で働くことが可能で、在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人が対象です。
現在11の産業分野(外食、宿泊、農業など)で受け入れが可能で、在留期間の制限がなく、家族の帯同も認められています。
また、日本語要件についても違いがあります。特定技能1号では日本語能力試験N4以上または同等レベルの試験合格が必要ですが、特定技能2号では日本語試験は不要(外食と漁業はN3合格が必要)となっています。
結論として
・特定技能1号は「即戦力として働ける外国人を短期間(最長5年)雇用するための制度」。
・特定技能2号は「熟練した技能を持つ外国人を長期間(無期限)雇用し、企業のコア人材として活躍してもらうための制度」です。
企業がどちらの制度を活用するかは、業界のニーズと雇用戦略に応じて選択することが重要です。
合わせて知りたい技能実習生と特定技能外国人の違いとは?
| 比較項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 発展途上国への技能移転(国際貢献) | 即戦力となる外国人労働者の受け入れ(労働力不足対策) |
| 在留期間 | 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) | 最長5年(特定技能1号)または無期限(特定技能2号) |
| 転職・転籍 | 原則不可 | 条件付きで可能 |
| 対象分野 | 91職種167作業(主に製造業、農業、建設など) | 16分野(介護、外食、建設、宿泊業など) |
| 受け入れ要件 | 技能実習計画の認定が必要 | 試験合格または技能実習2号を良好に修了 |
技能実習制度と特定技能制度の最大の違いは、その目的と仕組みです。
技能実習制度は発展途上国への技能移転を目的とした国際貢献の制度です。
企業は外国人技能実習生を受け入れ、技術や知識を伝え、最終的に実習生が母国で活かせるよう指導します。
そのため、在留期間は最長5年と制限され、転職(転籍)は原則不可です。
一方、特定技能制度は日本の労働力不足を補うための制度です。
特定産業分野で即戦力として働ける外国人を受け入れます。
特定技能外国人に関しては転職(転籍)も条件付きで認められており、より柔軟な雇用が可能になっています。
どちらを選ぶべきか?技能実習制度と特定技能制度の選択基準
企業が外国人材を採用する際、技能実習制度と特定技能制度のどちらを選ぶべきかは、経営の目的や業種、人手不足の深刻度によって異なります。
技能実習制度を選ぶべき企業
- 国際貢献を重視し、技能移転を目的とした受け入れをしたい場合
- 人材育成に時間をかけられる環境がある場合
- 一定期間(最長5年)で人材を確保したい場合
技能実習制度は、本来、日本の技術を発展途上国に移転することを目的としており、企業は外国人実習生に対し、一定期間にわたり技術指導を行うことが求められます。
また製造業や農業などの分野では、比較的短期間で育成可能な作業が多いため、この制度が適しています。
ただし、転籍は原則不可のため、長期的なキャリア形成を希望する外国人労働者にとっては選択肢が限られる点に注意が必要です。
特定技能制度を選ぶべき企業
- 即戦力となる人材を求めている場合
- 長期間(5年以上)働いてもらいたい場合
- 転職のリスクがあることを理解している場合
一方、特定技能制度は、慢性的な人手不足に直面している企業に適した制度です。
特に、介護や建設、外食業などは人材確保が難しく、日本人だけでは労働力が足りない状況にあり、特定技能制度を利用することで特定技能1号では最長5年、2号では在留期間の制限がなしで、長期的な雇用をしやすくなっています。
結論として言えることは、 企業が育成を前提とした外国人雇用を考えるなら技能実習制度を活用すべきでしょう。
そして、即戦力を求める場合や長期雇用を視野に入れる場合は、特定技能制度の方が適しています。
企業が特定技能外国人を受け入れるメリットとデメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 人材不足の解消 | 即戦力として活躍し、慢性的な人手不足を補える | 業種によっては日本人との協働が難しくなる場合がある |
| 雇用コスト | 日本人採用よりコストが抑えられる可能性がある | 在留資格申請や支援体制構築に追加コストがかかる |
| 労働意欲・定着率 | ミャンマー人材などは勤勉で長期就業意欲が高い | 文化や価値観の違いから、職場環境に適応できないケースも |
| 制度利用の手続き | 技能実習に比べ手続きがシンプルで柔軟な雇用が可能 | 特定技能1号では企業が支援体制を整える義務がある |
| 長期的な雇用 | 特定技能2号では在留期間の上限がなく、定着しやすい | 特定技能1号は最長5年のため、長期雇用には課題がある |
企業にとって特定技能外国人を受け入れる最大のメリットは、即戦力の人材を確保できることです。
特に、介護、外食、建設業などの人手不足が深刻な業界では、即戦力として働ける外国人材の確保は大きな支援となります。
一方で、デメリットとして特定技能1号では企業が外国人材の生活支援を行う義務があり、住宅手配や日常生活のフォローが必要なこと。
さらに在留資格の申請や更新手続きなど、管理業務も発生するため、社内に外国人雇用に関するノウハウを蓄積することが求められます。
ただし、こうしたデメリットは、事前の計画と適切な支援体制の構築によって十分に対策できます。
企業が特定技能外国人を受け入れる際には、人材の育成や支援体制の整備、文化の違いを理解することが重要です。
この章では、企業が特定技能外国人を受け入れるメリットとデメリットについて詳しく解説します。
企業が特定技能外国人を受け入れる5つのメリット
- 人手不足の解消:特定技能外国人の受け入れにより、慢性的な人手不足を補うことができます。
- 即戦力の確保:特定技能外国人は一定の技能と日本語能力を有しており、採用後すぐに戦力として活躍が期待できます。
- 雇用人数の柔軟性:特定技能制度では、受け入れ人数に制限がないため、企業のニーズに合わせた人材確保が可能です。
- 職場の活性化:多様な文化背景を持つ人材の参入により、職場の活性化や新しい視点の導入が期待できます。
- 海外展開の足がかり:外国人材の雇用を通じて、将来的な海外進出や国際的なビジネス展開の基盤を築くことができます。
特定技能外国人の受け入れは、企業にとって即戦力の確保や人手不足の解消といった大きなメリットがあります。
特定技能制度では、一定の技能と日本語能力を持つ人材を採用できるため、教育や研修にかかる時間とコストを削減できるだけでなく、受け入れ人数に制限がないため、企業の状況に応じた柔軟な人材配置が可能です。
さらに、多様な文化背景を持つ人材の参入は、職場の活性化や新たな視点の導入につながり、組織全体のイノベーションを促進します。
将来的には、外国人材とのネットワークを活用し、海外展開や国際的なビジネスチャンスを広げる足がかりともなり得ます。
特定技能制度を利用するデメリットとリスク
特定技能制度の主なデメリット
- 支援義務の負担:特定技能1号では、企業が外国人労働者の生活支援を行う義務があり、負担が増える。
- 文化・言語の壁:日本の職場文化や生活習慣に慣れるまで時間がかかり、コミュニケーションの問題が発生しやすい。
- 在留資格の更新手続き:特定技能1号は最長5年のため、更新手続きが必要であり、行政手続きの負担がある。
- 転職・転籍のリスク:外国人労働者が他社へ転職する可能性があり、人材流出のリスクが伴う。
- 法令遵守の複雑さ:入管法や労働法の理解が必要で、違反すると罰則や企業の信用失墜につながる。
特定技能制度を利用する際の最大の課題は、企業の支援義務と法令遵守の負担です。
特定技能1号では、企業が外国人の住居確保や生活サポートを提供する義務があり、これを怠るとトラブルの原因になります。
中には日本の職場文化や言語の違いがストレスとなり、離職や生産性の低下を引き起こす可能性があります。
さらに、特定技能1号の在留期間は最長5年であり、定期的な更新手続きが必要です。
これに加え、特定技能労働者は一定の条件下で転職が可能なため、企業が育成した人材が他社に移ってしまうリスクもあります。
だからこそ企業側は適切なキャリアパスを用意し、職場環境を改善することで、定着率を高める工夫が求められます。
なお法令遵守の面では、入管法や労働法の規定を正しく理解し、適切な手続きを進めることが不可欠です。
専門機関と連携し、定期的な研修や法令チェックを実施することで、コンプライアンス違反のリスクを軽減できます。
デメリットを理解し、事前に対策を講じることで、特定技能制度の活用をより効果的に進めることが可能になるでしょう。
特定技能外国人の在留資格と受け入れ手続き
| 手続きのステップ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. 受け入れ企業の準備 | 特定技能外国人の雇用を検討し、必要な条件や支援体制を整備する。 |
| 2. 求人募集・選定 | 送り出し機関、登録支援機関と連携し、特定技能外国人を選定する。 |
| 3. 在留資格の申請 | 特定技能1号または2号の在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局へ申請。 |
| 4. 在留資格取得・ビザ申請 | 日本の在外公館(大使館・領事館)でビザを申請し、取得する。 |
| 5. 日本入国・雇用開始 | 日本へ入国し、企業と雇用契約を結び、就労開始。特定技能1号の場合は支援体制が必要。 |
特定技能外国人を受け入れるには、企業は事前準備、在留資格の取得、雇用後のフォローアップといった一連のプロセスを確実に進める必要があります。
まず、対象分野の確認や支援体制の整備を行い、適切な人材を選定します。その後、在留資格の申請やビザ取得を経て、日本での就労が可能となります。
特定技能1号では支援体制の構築が求められるため、企業は外国人が円滑に働ける環境を整えることが重要です。
この章では、特定技能外国人の在留資格と受け入れ手続きについて詳しく解説します。
1. 受け入れ企業の準備
まず、企業は特定技能外国人の受け入れを決定し、対象となる分野を確認する必要があります。
特定技能制度は、介護・建設・外食業・農業・宿泊業、自動車運送業などの16分野が対象となっており、企業は自社の業種が該当するかどうかを事前に確認しましょう。
また特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業は登録支援機関と契約するか、支援計画を策定して自社で支援を行う必要があります。
支援内容には、日本での生活支援(住居の確保、銀行口座開設、行政手続きのサポート)や、職場での相談対応などが含まれます。
また、外国人労働者が安心して働けるように、日本語学習のサポートを行うことも推奨されます。
企業は、特定技能外国人を受け入れるにあたり、受け入れ態勢を整えることが不可欠です。
雇用契約の締結、労働条件の明確化、就労環境の整備などを事前に行い、外国人労働者が円滑に業務を開始できるよう準備を進める必要があります。
2. 求人募集・選定
特定技能外国人を採用するためには、企業は送り出し機関や登録支援機関と連携し、適切な候補者を選定するプロセスを進めます。
送り出し機関は、外国人労働者を日本へ送り出す役割を担っており、候補者のスクリーニングや事前教育などを行います。
特定技能外国人の採用にあたっては、技能評価試験および日本語試験に合格していることが必須要件となります。
各業界ごとに定められた技能試験をクリアし、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、またはそれに相当する試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験が免除される場合があり、比較的スムーズに採用を進めることが可能です。
企業は、候補者の経験や能力だけでなく、適性や職場環境との相性を考慮して採用を進めることが重要です。
面接や適性テストを活用し、企業文化に適応できるかどうかを慎重に見極めることが、長期的な雇用の成功につながります。
ミャンマー・ユニティが選ばれる理由
豊富な求職者・透明性のある募集体制
- ブローカーを一切使わず透明性のある募集を実施
- ミャンマー全土の提携日本語学校より日本で働きたい求職者が紹介される
- 日本語学校無料オンライン教育によりミャンマー全土から日本で働きたい求職者を募集
- 特定技能候補者に対し手数料以外の費用は徴収せず負担に配慮した費用体系
eラーニングを活用した教育体制
- 『MJ Space』にてに日本語eラーニング動画無料配信
- ミャンマー・ユニティの蓄積されたノウハウによるオリジナル教育コンテンツ
- ミャンマー人求職者はスマートフォンによりいつでもどこでも学習が可能
- 日本語教育コンテンツはN5~N2レベルまでを網羅
- 2024年3月より、介護日本語評価試験および介護・外食・農業の技能評価試験学習機能を搭載
3. 在留資格の申請
特定技能外国人を正式に雇用するためには、在留資格「特定技能1号」または「特定技能2号」を取得する必要があります。
この手続きは、企業が主導して行い、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を提出します。
申請の際には、雇用契約書、雇用条件書、支援計画書(特定技能1号の場合)、技能試験や日本語試験の合格証明書、企業の事業計画書など、さまざまな書類を準備する必要があります。
特定技能2号は、熟練技能を持つ労働者が対象で、在留期間に制限がないため、長期的な雇用を希望する企業には適した選択肢となります。
申請が受理されると、在留資格認定証明書が発行され、次のステップとして、外国人本人がビザ申請を行う準備を進めることになります。
4. 在留資格取得・ビザ申請
在留資格認定証明書が発行された後、外国人労働者は自国の日本大使館または領事館でビザ申請を行い、発給を受ける必要があります。
この手続きには、パスポート、在留資格認定証明書、ビザ申請書、企業の雇用契約書などが必要となります。
ビザが発給されると、外国人労働者は正式に日本へ入国する準備が、ほぼ整います。
この段階では、企業側は入国後の生活支援の準備を進めるために以下のようなサポートを行いましょう。
- 住居の確保(社員寮の準備や不動産会社との調整)
- 生活オリエンテーション(公共交通機関の利用方法、ゴミの分別ルールなど)
- 行政手続きのサポート(住民登録、健康保険加入、銀行口座開設など)
特に、特定技能1号の外国人は、日本の生活に不慣れな場合が多いため、企業は事前に支援計画を策定し、スムーズに生活を開始できる環境を企業側が整える必要があります。
5. 日本入国・雇用開始
ビザを取得した外国人労働者は、正式に日本へ入国し、企業と雇用契約を締結したうえで就労を開始します。
特定技能1号の場合、登録支援機関は法的に定められた支援を提供する義務があり、具体的には、以下のようなサポートが求められます。
- 職場環境への適応支援(業務内容の説明、労働条件の再確認)
- 生活サポート(医療機関の利用方法、生活ルールの説明)
- 定期的な面談・相談(仕事や生活の悩みを聞く機会を設ける)
特定技能2号の場合は、在留期間の制限がなく、家族の帯同も認められるため、長期的な雇用を考える企業にとって有利な選択肢となります。
また、特定技能1号の外国人は在留期間が最長5年であるため、その後のキャリアプランも考慮することが重要です。
例えば、特定技能2号への移行を目指す場合、追加の試験合格が必要となるため、企業側は事前に情報提供を行い、外国人労働者のスキル向上を支援することが求められます。
特定技能外国人に関するまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能制度の目的:日本の深刻な人手不足を補うため、即戦力となる外国人材を受け入れる制度。
- 特定技能1号と2号の違い:1号は最長5年の在留、2号は無期限で家族の帯同が可能。
- 受け入れの流れ:求人募集から在留資格申請、支援計画の策定、雇用契約までの明確なプロセスが必要。
- メリットとデメリット:人材確保の利点がある一方で、支援義務や転職リスクなどの課題もある。
- 適切な支援の重要性:企業は法令遵守と職場環境整備を徹底し、外国人労働者の定着を促進する必要がある。
この記事では、特定技能制度の基本概要やメリット・デメリット、受け入れ手続きについて詳しく解説しました。
特定技能制度を活用することで、人手不足に悩む企業も即戦力となる外国人材を確保できます。しかし、適切な手続きとサポートがなければ、雇用の成功は難しくなります。
外国人材の受け入れに不安がある場合は、ミャンマー政府認定圧倒的No.1の送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」を活用するのがおすすめです。
「ミャンマー・ユニティ」では、優れた外国人労働者の選定から在留資格取得のサポート、定着支援まで一貫した支援を提供しています。
▶詳細はこちら:ミャンマー・ユニティにお問合せ無料でご提供しております