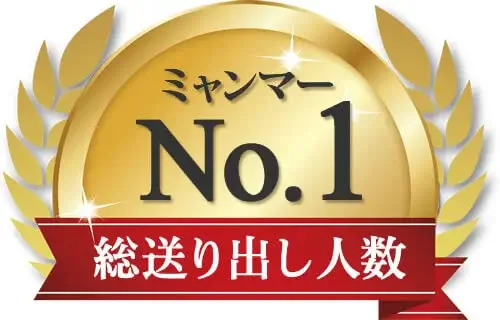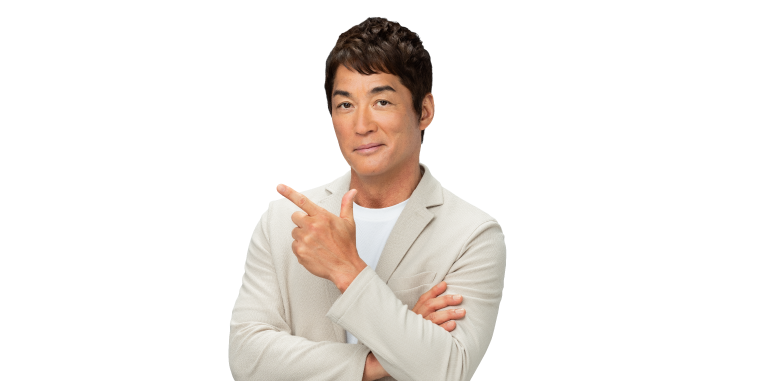特定技能1号・2号の職種の違いと取得方法・転職条件を徹底解説!
人手不足が深刻化する中、外国人材の採用を検討している企業も多いのではないでしょうか。
しかし、「どの在留資格を選べばよいのか」「手続きが複雑で不安」と感じている経営者の方も少なくありません。
特定技能制度は、日本の人材不足を補うために導入された在留資格の一つです。
特定技能1号と2号では、対象分野や求められる技能水準、在留期間の条件が異なります。
この記事では、特定技能制度の概要や活用のポイントについて詳しく解説しています。
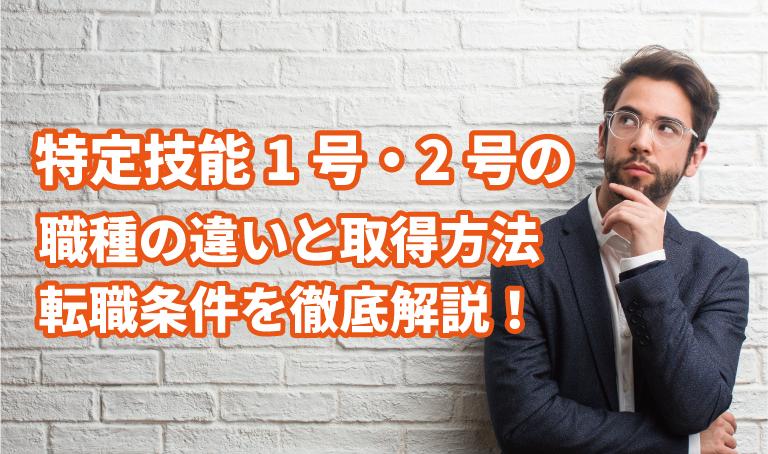
目次
特定技能とは?基本概要と16分野の対象業種をまずは理解する
特定技能の基本概要 - 5つのポイント
- 人手不足解消のための在留資格:2019年に導入され、人材不足の深刻な16の特定産業分野で外国人の雇用を可能にする。
- 2種類の在留資格:「特定技能1号」は一定の専門性と日本語能力を持つ外国人向けで、「特定技能2号」はより高度な技能を持つ外国人向け。
- 16の対象分野:介護、外食業、自動車運送業、農業など、日本の主要産業の労働力確保を目的とする。
- 試験制度と技能実習からの移行:対象分野ごとに試験があり、技能実習2号を修了した外国人は試験免除で移行可能。
- 企業の義務と支援体制:特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、生活・業務面での支援を提供する義務がある。
特定技能とは、日本政府が2019年に導入した外国人向けの在留資格の一つです。
2025年2月現在、人材不足が深刻な16の産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れられるようになりました。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、比較的基本的な業務に従事する外国人向けで、在留期間の上限は5年です。
一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人向けで、条件を満たせば家族の帯同も認められ、在留期間の更新が可能です。
次の表のように特定技能1号と2号には違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象者 | 基本的な業務に従事する外国人 | 高度な技能を持つ外国人 |
| 在留期間 | 最長5年(更新あり) | 制限なし(更新可能) |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
| 技能要件 | 技能評価試験合格または技能実習2号を良好に修了 | 高度な技能評価試験合格 |
| 受け入れ企業の義務 | 生活・業務支援が必要 | 支援義務なし |
また特定技能の対象分野は、介護、自動車運送業、農業、外食業など、日本の産業を支える重要な分野が含まれています。
外国人は分野ごとの試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで特定技能への移行が可能です。
2024年3月における特定技能制度の主な変更点
| 変更内容 | 詳細 |
|---|---|
| 受け入れ見込み数の再設定 | 2024年4月からの5年間で、特定技能外国人の受け入れ見込み数が約82万人に設定され、前回の約34.5万人から約2.4倍に増加しました。 |
| 対象分野の追加 | 新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が特定技能1号の対象として追加されました。 |
| 製造業分野の業務区分の拡大 | 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業」へ名称変更され、7つの業務区分が追加され、合計10業務区分となりました。 |
| 造船・舶用工業分野の業務再編 | 既存の6業務区分が3区分に再編され、業務範囲の拡大と新たな作業が追加されました。 |
| 飲食料品製造業分野の対象事業所の拡大 | スーパーマーケットにおける「惣菜などの製造」も特定技能の対象業務として認められるようになりました。 |
2024年3月、日本政府は特定技能制度に関する重要な改正を行いました。
まず、特定技能外国人の受け入れ見込み数が大幅に増加し、2024年4月からの5年間で約82万人に設定されました。
これは前回の約34.5万人から約2.4倍の増加となります。
さらに、人手不足が深刻な「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに特定技能1号の対象分野として追加されました。
製造業分野では「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業」へと名称が変更され、7つの業務区分が新たに追加され、合計で10業務区分となりました。
これにより、より多くの業種で特定技能外国人の受け入れが可能となります。
また造船・舶用工業分野では、既存の6つの業務区分が3つに再編され、業務範囲の拡大と新たな作業が追加されました。
飲食料品製造業分野においても、総合スーパーマーケット※や食料品スーパーマーケット※での「惣菜などの製造」が特定技能の対象業務として認められるようになり、受け入れ可能な事業所の範囲が広がりました。
これらの改正により、多くの業界で外国人材の活用が進み、人手不足の解消に寄与することが期待されています。
※食料品製造を行うものに限る
【分野別】特定技能の職種一覧|どの業種でどう働けるのか?
| 分野 | 主な職種 | 必要な試験・資格 |
|---|---|---|
| 介護 | 介護業務全般 | 介護技能評価試験、介護日本語評価試験 |
| ビルクリーニング | 建物内外の清掃業務 | ビルクリーニング分野特定技能評価試験 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 鋳造、鍛造、金属プレス加工など | 各職種ごとの特定技能評価試験 |
| 建設 | とび、型枠施工、鉄筋施工など | 建設分野特定技能評価試験 |
| 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工など | 造船・舶用工業分野特定技能評価試験 |
| 自動車整備 | 自動車の点検・修理 | 自動車整備分野特定技能評価試験 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 | 航空分野特定技能評価試験 |
| 宿泊 | ホテルのフロント、接客、清掃 | 宿泊分野特定技能評価試験 |
| 農業 | 耕種農業(野菜・果樹)、畜産農業 | 農業分野特定技能評価試験 |
| 漁業 | 漁業全般、養殖業 | 漁業分野特定技能評価試験 |
| 飲食料品製造業 | 食品加工、調理 | 飲食料品製造業分野特定技能評価試験 |
| 外食業 | レストランでの調理・接客 | 外食業分野特定技能評価試験 |
| 林業 | 森林管理、木材生産 | 林業分野特定技能評価試験 |
| 木材産業 | 製材、合板・建材製造 | 木材産業分野特定技能評価試験 |
| 自動車運送業 | トラック・タクシー・バス運転 | 自動車運送業分野特定技能評価試験 |
| 鉄道 | 駅務、保守、運転補助 | 鉄道分野特定技能評価試験 |
| 分野 | 主な職種 | 必要な試験・資格 |
|---|---|---|
| 外食 | 飲食物調理、接客、店舗管理など | 特定技能2号外食建設技能試験 |
| 宿泊 | フロント、企画・広報、接客など | 特定技能2号宿泊技能試験 |
特定技能制度は、特に人手不足が深刻な上記の表の16の分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が即戦力として採用されるようになっています。
例えば、介護業界では、特定技能を取得した外国人が高齢者の生活支援や身体介護を行い、日本人スタッフと協力して現場を支えています。
建設業界では、「とび」「型枠施工」などの技能を持つ外国人が橋梁工事やビル建設の現場で活躍しています。
技能実習を終えた外国人が特定技能に移行することで、さらに高度な業務に従事できるようになり、企業にとって貴重な戦力となっています。
また飲食業界では、特定技能取得者が日本食レストランやホテルの厨房で調理を担当し、日本人スタッフと共に高品質なサービスを提供しています。
最近では、スーパーマーケットの惣菜部門も特定技能の対象となり、食品製造分野の拡大が進んでいます。
企業側にとって、特定技能制度を活用することで、慢性的な人材不足の解消だけでなく、多様な文化を持つスタッフとの協働が可能になります。
そもそも、なぜ特定技能1号と2号で活躍できる分野と業種が違うのか?
特定技能1号と特定技能2号で活躍できる分野と業種が異なるのは、それぞれの制度の目的と求められる技能水準が異なるためです。
特定技能1号は、比較的基本的な業務を行う外国人向けの資格であり、人手不足が深刻な16の産業分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。
1号では、専門的な技術よりも実務レベルの作業が求められ、試験によって技能や日本語能力を確認します。
また、在留期間の上限が5年で、家族の帯同は認められていません。
一方で、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人向けの資格です。
特定技能2号では、熟練技術を持つ外国人を長期的に受け入れるため、在留期間の更新が可能であり、家族の帯同も認められています。
このように、特定技能1号は「即戦力としての外国人労働者」を受け入れる制度であり、特定技能2号は「高度な技能を持つ専門職」を対象とするため、活躍できる分野が異なっているのです。
特定技能追加予定の職種・業種(2025年2月最新版)について
2024年3月29日の閣議決定により、特定技能制度の対象分野が拡大されました。
新たに追加された分野は以下の4つです。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
これらの分野では、深刻な人手不足が課題となっており、特定技能外国人の受け入れが期待されています。
また既存の「工業製品製造業」「造船・舶用工業」「飲食料品製造業」の3分野においても、新たな業務の追加や業務区分の再編が行われています。
具体的には、工業製品製造業では「紙器・段ボール箱製造」「コンクリート製品製造」など7つの業務が追加され、造船・舶用工業では業務区分の再編と作業範囲の拡大が実施されています。
これらの変更により、特定技能外国人の受け入れ見込み数は総計で約82万人に拡大され、各産業分野の人材不足解消と経済活性化が期待されています。
なお、ミャンマー・ユニティでは外国人雇用に関しての最新情報を紹介するセミナーや、技能実習生が働いている様子を見ることができる見学会の動画など多数ご用意しております。
気になられた方は、合わせてコチラ(録画視聴申込受付中セミナー 一覧)もご確認ください。
出典:出入国管理庁特定技能の取得方法と各分野の試験情報
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象分野 | 16分野(介護、自動車運送業建設、外食業など) | 11分野(外食、宿泊など)2分野(建設、造船・舶用工業) |
| 取得方法 | 技能評価試験+日本語試験、または技能実習2号を良好に修了 | 高度な技能評価試験の合格が必要 |
| 試験内容 | 業種ごとに異なる技能評価試験+日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT Basic A2) | より高度な技能試験(試験科目が多い) |
| 在留期間 | 最長5年(更新あり、延長なし) | 更新回数に制限がない(永続的な在留が可能) |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子ども) |
特定技能は1号と2号で取得方法や試験内容には大きな違いがあります。
特定技能1号では、16分野の業種で一定の技能を持つ外国人を受け入れます。
取得方法は、各分野ごとの技能試験と定められたレベルの日本語試験に合格することが基本です。
また、技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除されます。
試験の難易度は比較的低く、実務レベルの知識や技術が問われます。ただし、1号の在留期間は最長5年であり、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は、より高度な技能を必要とする業種向けです。現在は外食や宿泊など11分野が対象となっています。
2号の取得には、より専門的な技能試験の合格が求められます。
試験の難易度も1号に比べて高く、実務経験や高度な技術が必要となるため、特定技能1号からのステップアップを目指す人向けの資格となっています。
この章では、特定技能1号と2号の取得方法について詳しく解説します。
特定技能1号と2号の取得方法と取得の流れ|共通点と違いを解説
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象分野 | 16分野(介護・外食業・建設など) | 11分野(外食や宿泊など) |
| 取得方法 | 特定技能評価試験+日本語試験、または技能実習2号を良好に修了 | 特定技能評価試験(より高度な技能が必要) |
| 試験の難易度 | 基本的な技能と日本語の理解度を問う | 熟練技能の証明が必要(より専門的な試験) |
| 取得の流れ | ①試験合格 ②雇用契約 ③在留資格申請 ④就労開始 | ①試験合格 ②雇用契約 ③在留資格申請 ④就労開始(ただしより厳しい審査あり) |
| 在留期間 | 最長5年 | 更新回数に制限がない(長期在留・永住も視野に) |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子ども) |
特定技能1号と2号は、どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、取得方法や流れに違いがあります。
特定技能1号は、16の産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れるための制度です。
取得には「特定技能評価試験」と「日本語試験(JLPT N4)または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT Basic A2)」に合格するか、「技能実習2号」を良好に修了する必要があります。
特定技能1号取得の流れは「①試験合格→②雇用契約締結→③在留資格申請→④就労開始」というステップで進みます。
一方、 特定技能2号は外食や宿泊などの11分野で、より高度な技術を持つ外国人を長期的に雇用するための資格です。
試験の内容は専門性が高く、熟練した技能を証明する必要がありますが取得の流れは基本的に特定技能1号と同じです。
ただし、年々審査基準が厳しくなっています。
現時点での特定技能2号の必要な実務経験と日本語要件は以下の図をご参照ください。
| 分野 | 技能に関する評価 | 実務経験 | 日本語要件 |
|---|---|---|---|
| ビルクリーニング |
|
「特定建築物」(建築物衛生法2条1項)の建築物内部の清掃又は「建築物清掃業」(同法12条の2第1項1号)、「建築物環境衛生総合管理業」(同項8号)の登録を受けた事業所が行う建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら2年間従事した経験 | なし |
| 製造 |
|
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の経験 | なし |
| 建設 |
|
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験(試験区分により年数は異なる) | なし |
| 造船 |
|
造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること | なし |
| 自動車整備 |
|
道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業所における3年以上の実務経験(技能検定の場合は受験資格で実務経験を判断か?) | なし |
| 航空 |
|
空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験 航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験 |
なし |
| 宿泊 |
|
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験 | なし |
| 農業 |
|
耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験 畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験 |
なし |
| 漁業 |
|
漁船法上の登録を受けた漁船において、場長を指揮監督する者若しくは作業員を指導しながら従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること 漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること |
あり |
| 飲食料品製造 |
|
飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(管理等実務経験)を2年以上有すること | なし |
| 外食 |
|
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験 | あり |
特定技能1号と2号に求められる日本語のレベルは?
特定技能1号と2号では、求められる日本語のレベルにも下記の表のような違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 求められる日本語レベル | 基本的な日常会話や業務指示の理解が必要 | 高度な専門用語や複雑な指示の理解が求められる |
| 試験要件 | 「JLPT N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)」合格 | 特定の日本語試験の要件なし(分野による外食と漁業はN3合格が必要)が、実務での習得が前提) |
| 具体的な能力 | 簡単な文章の読解・日常会話・業務指示の理解・簡単な報告 | 専門用語の習得・高度な業務指示の理解・専門的な報告業務 |
| 介護分野の特例 | 「介護日本語評価試験」の合格が必要 | 特定の試験要件はないが、高度な日本語能力が求められる |
| 企業側の対応 | 入社後の日本語教育を充実させることが望ましい | 既に高度な日本語能力を備えていることが前提 |
特定技能1号では、基本的な日常会話や業務上の指示を理解できる程度の日本語能力が求められます。
そのため、取得には「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic A2)」に合格することが必要です。
N4レベルの日本語は、簡単な文章を読んだり、日常的な会話ができる程度とされています。
例えば、上司からの業務指示を理解し、簡単な報告ができるレベルが求められています。
ただし、特定技能1号のうち「介護」分野に関しては、専門的な日本語能力も求められ、「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
また、「自動車運送業」分野に関しては、タクシードライバー・バスドライバーについては「日本語能力試験(JLPT)N3以上」の合格が必須です。
一方、特定技能2号には、基本的には特定の日本語試験の合格要件はありません。(外食と漁業はN3合格が必要)
特定技能2号は高度な技術を持つ熟練労働者向けの在留資格であり、業務上必要な日本語は十分に習得していることが前提とされているためです。
とはいえ、業務を遂行する上で高度な専門用語や複雑な指示を理解する必要があるため、特定技能1号の求めるN4レベルよりさらに高い以上の日本語能力が実務的に求められます。
【特定技能1号・2号】各分野の試験の申し込み方法と受験対策について
特定技能1号・2号の試験申し込み方法と受験対策について解説します。
特定技能1号の試験申し込み方法
特定技能1号を取得するには、各分野ごとの「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。
申し込みは、各分野の試験実施機関の公式サイトを通じて行います。例えば、介護分野の場合は「介護技能評価試験」、外食業では「外食業技能測定試験」があります。
受験は日本国内だけでなく、海外の指定試験会場でも可能です。申し込みはオンラインで行うことが一般的で、試験日程や会場は分野ごとに異なります。
特定技能2号の試験申し込み方法
特定技能2号の試験は、外食や宿泊など11分野で実施されています。
試験内容は特定技能1号よりも高度で、熟練した技術を証明するための試験が必要です。申し込み方法は、各業界の試験実施機関の公式ウェブサイトから行います。
受験対策のポイント
試験対策としては、まず過去問題やテキストを活用し、試験の傾向を把握することが重要です。
また、試験対策講座を受講することで、より効率的に学習を進めることができます。
特に、日本語試験はJLPT N4以上または国際交流基金の日本語基礎テスト(JFT Basic A2)のレベルが求められるため、日常会話や業務用語の習得も欠かせません。
特定技能2号を目指す場合は、実務経験を積みながら専門知識を深めることが合格への近道となります。
ここまで特定技能とは何か、1号と2号の違いや取得方法などについて解説させて頂きました。
次の章では、特定技能1号と2号の転職についての違いや条件について詳しくご紹介します。
【特定技能1号・2号】転職条件の違いと共通点
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象業種 | 16分野全般(介護、外食、宿泊など) | 外食や宿泊などの11分野 |
| 転職時の必要条件 | 同一の業務区分内であること、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること | 同一の業務区分内であること、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること |
| 在留資格の更新 | 最長5年 | 更新回数に制限がなく、 |
| 家族の帯同 | 認められない | 認められる(条件付き) |
| 転職の目的 | 即戦力としての即時転職・人手不足解消 | 長期的な定着・高度技術の活用 |
特定技能1号と2号の転職条件には明確な違いがあります。
1号は、介護・外食業・宿泊建設など16分野を対象とし、転職時には基本的な技能試験と日本語能力の証明が求められます。
企業は即戦力を求めるため、比較的転職がしやすい制度となっています。
一方、2号は外食や宿泊などの11分野が対象で、転職には高度な技能試験の合格や実務経験の証明が必要です。
特定技能1号の転職条件とルール
特定技能1号の転職条件とルールについて、以下のポイントにまとめました。
- 在留資格変更許可申請の必要性: 特定技能1号の外国人が転職する際には、新たな受け入れ企業ごとに在留資格変更許可申請が必要です。
- 同一業種・業務への転職: 現在の業種や業務内容と同じ分野への転職の場合、同一の業務区分内であること、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であることが条件です
- 異なる業種・業務への転職: 異なる業種や業務内容への転職を希望する場合、新たな分野の技能評価試験に合格する必要があります。
- 在留期間の制限: 特定技能1号の在留期間は通算で最長5年と定められており、転職後もこの期間内での就労が求められます。
- 手続きの注意点: 転職時には、旧受け入れ企業と新受け入れ企業の双方で必要な手続きを適切に行うことが重要です。
特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者が転職するたびに新たな受け入れ企業での在留資格変更許可申請が必要となります。
これは特定技能が特定の企業や業務に紐づいているためです。
同じ業種や業務内容への転職であれば、既に取得した技能試験や日本語能力試験の資格が有効ですが、異なる分野への転職を希望する場合、新たな分野の試験に合格する必要があります。
また特定技能1号の在留期間は通算で最長5年と定められており、転職後もこの期間内での就労が求められます。
さらに、転職に伴う手続きとして、旧受け入れ企業と新受け入れ企業の双方で必要な手続きを適切に行うことが重要です。
これらの手続きを怠ると、在留資格の更新や新たな就労に支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。
特定技能2号の転職条件とルール
特定技能2号は、外食や宿泊などの11分野で実施されております。
特定技能2号の転職条件とルールについては、次が理解しておきたい重要ポイントです。
- 対象分野: 特定技能2号は、外食や宿泊などの11分野で実施されております。
- 在留期間: 在留期間は3年、1年、または6か月ごとの更新が可能で、更新回数に制限はありません。
- 技能水準: 高度な技能が求められ、各分野で定められた試験に合格する必要があります。
- 日本語能力: 原則として日本語能力試験は不要(外食と漁業はN3合格が必要)ですが、業務上必要な日本語能力が求められます。
- 家族の帯同: 一定の条件を満たすことで、配偶者や子供の帯同が認められます。
そもそも特定技能2号は、特定の産業分野において熟練した技能を持つ外国人が就労するための在留資格です。
特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、各分野で定められた試験に合格することが必要です。
在留期間は更新が可能ですが対象となる分野は1号に比べて限られており、転職を希望する場合は新たな受け入れ企業での在留資格変更許可申請が必要になります。
特定技能外国人が転職できない条件とは?
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 在留資格の期限切れ | 特定技能の在留期限が切れている場合、転職は認められず、日本に滞在することもできません。 |
| 転職先が特定技能の対象業種外 | 特定技能の対象業種(1号は16分野、2号は11分野)以外の職種には転職できません。 |
| 試験要件を満たしていない | 転職先の分野で必要な特定技能評価試験に合格していない場合、転職はできません。 |
| 受け入れ企業が基準を満たしていない | 転職先の企業が、特定技能外国人の受け入れに必要な基準(労働条件、支援体制など)を満たしていない場合、転職は認められません。 |
| 不適切な理由での転職 | 勤務態度不良や契約違反を理由に雇用契約が終了した場合、転職が困難になることがあります。 |
特定技能外国人が転職できない理由には、在留資格の問題や試験要件の未達成など、さまざまな要因があります。
まず、在留期限が切れている場合、更新手続きを行わない限り転職は不可能であり、日本での滞在自体が認められなくなります。
また、転職先が特定技能の対象分野外である場合も転職はできません。
例えば、特定技能1号の「外食業」から「IT業界」への転職は許可されません。
特定技能外国人が転職するためには、新たな分野の技能評価試験に合格する必要があります。
例えば、「農業」分野の特定技能1号を持つ外国人が「建設業」へ転職する場合、建設分野の技能評価試験に合格しなければなりません。
もちろん、転職先の企業が特定技能の受け入れ基準を満たしていない場合も転職は認められません。
転職先の企業に適切な労働条件の確保や、外国人支援体制の整備などがなく、基準を満たしていない場合も特定技能外国人は、その企業への転職は行えません。
このような場合、特定技能外国人は新たな雇用先を見つけるまでの間、在留資格の期限内で就職活動を行う必要があります。
しかし、期限内に転職先が見つからない場合、最終的には帰国を余儀なくされてしまうでしょう。
特定技能1号と2号の職種まとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能1号の対象分野: 16の特定産業分野で、主に人手不足が深刻な業種が含まれます。
- 特定技能2号の対象分野: 当初は建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみでしたが、現在では外食や宿泊など9分野が追加されています。
- 在留期間と更新: 特定技能1号は最長5年間で更新不可、2号は更新が可能で長期的な在留が認められます。
- 家族の帯同: 1号では基本的に認められませんが、2号では要件を満たせば可能です。
- 技能水準と試験: 1号は基礎的な技能試験と日本語能力試験の合格が必要で、2号はより高度な技能試験の合格や実務経験の証明が求められます。
この記事では、特定技能1号と2号の対象分野や在留条件、必要な技能水準について詳しく解説しました。
特定技能制度を活用することで、人手不足に悩む企業は即戦力となる外国人材を確保できます。
特に優秀な人材をお探しの企業様は、ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関である「ミャンマー・ユニティ」にお任せください。
ミャンマー・ユニティでは特定技能人材以外にも介護を含む技能実習生や高度人材(エンジニア・通訳)も日本に送り出しており、質の高い教育とサポート体制を数多くの企業様にご提供しております。
詳しい情報やお問い合わせは、以下のリンクからご確認ください。
無料でご提供しております