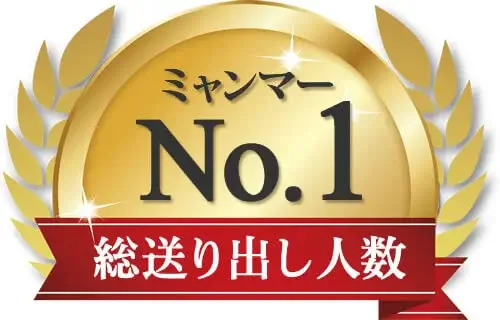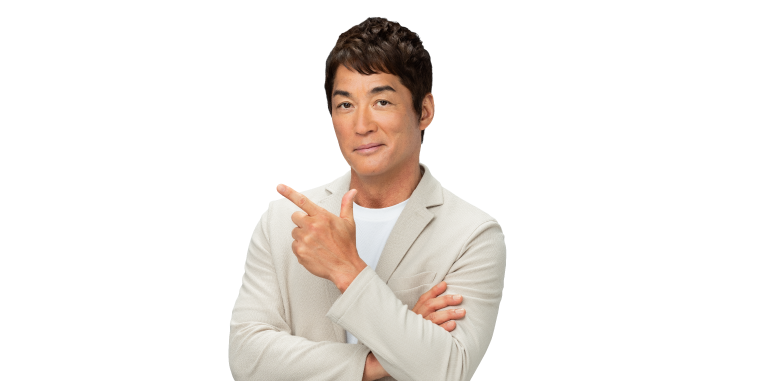登録支援機関とは?その役割から料金相場、登録支援機関の選び方も解説
外国人労働者を受け入れる際、煩雑な手続きや文化の違いへの対応に不安を感じていませんか?
特に初めて外国人材を採用する企業にとって、入国手続きや生活支援など、わからないことだらけで、不安が多いかもしれません。
実は、こうした課題を解決するために「登録支援機関」が重要な役割を果たします。
この記事では、登録支援機関とは何か、その役割や具体的な支援内容について詳しく解説しています。
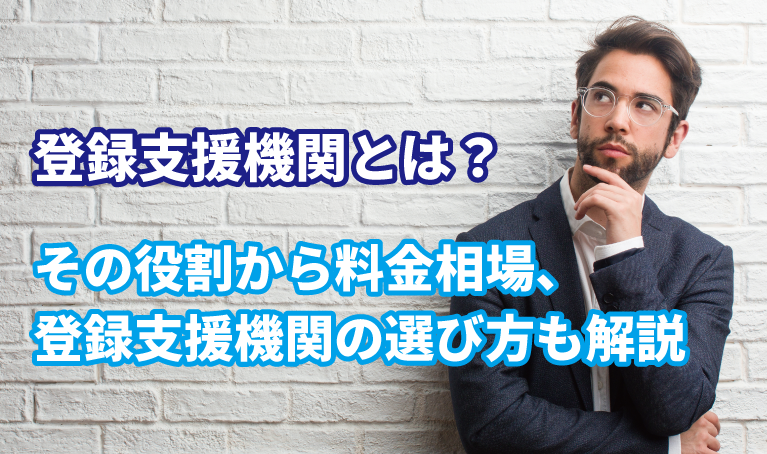
目次
登録支援機関とは?どういった機関で何をしてくれるの?
登録支援機関の概要
- 外国人労働者をサポートする機関
特定技能1号外国人が円滑に活動できるよう、受入企業から委託を受けて支援業務を行います。 - 義務的支援と任意的支援
義務的支援については最低ラインとして必ずしなければならないもので、任意的支援については義務的支援をスムーズに進めるためにした方がよいものとしてとらえるとよいでしょう。 - 支援計画書の作成と実施
入国から就労、生活支援までの詳細な計画を立案し、実行する役割を担います。 - 多様な登録主体
行政書士や社労士、業界団体など、条件を満たせば団体や個人でも登録可能です。 - 企業と外国人の架け橋
特定技能外国人の雇用がスムーズに進むよう、言語対応や法律遵守の観点から重要な役割を果たします。
登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活や就労を円滑に行えるようサポートする専門機関のことです。
この機関は、外国人労働者の受入企業が抱える複雑なさまざまな手続きを代行し、外国人労働者の就労支援を包括的に行ってくれます。
登録支援機関の業務は多岐にわたり、入国手続きや住宅確保、生活オリエンテーションの実施、日本語教育の提供、交流促進など、幅広い支援内容が含まれます。
また登録支援機関の支援業務は大きくわけて「義務的支援」と「任意的支援」の2つに分かれ、特定技能外国人が直面する、さまざまな問題を解決するために動いてくれます。
登録支援機関が求められる理由とその背景
登録支援機関が必要とされる背景には、外国人労働者の受入れが増加している現状と、それに伴う、いくつもの課題があります。
日本では深刻な人手不足を解消するために、特定技能制度を活用して外国人労働者を受け入れていますが、受入企業は外国人労働者を働かせる以外にもやらなければならないことが山のようにあります。
外国人労働者の受入企業が行う必要がある業務は、例えば、入国手続きや住民登録の同行、賃貸物件の契約サポートといった生活支援業務があります。
さらに、生活オリエンテーションを通じて日本のルールやマナー、交通機関の利用方法を教える必要もあります。
加えて、相談窓口の設置や定期的な面談を通じて、労働者の職場環境や生活の課題を解決する取り組みも求められていますが、これらの業務は、受入企業にとって大きな負担となるため、登録支援機関がサポート役として欠かせない存在となっています。
企業側が登録支援機関を利用するメリット
外国人労働者を受け入れる際に企業は単に労働者を雇用するだけでなく、入国手続き、住居の手配、生活支援、法令遵守など多くの追加業務を行わなければなりません。
当然ですが、これらの対応には専門知識や外国語力が必要で、人員や時間、労力の大きな負担となってしまいます。
そこで役立つのが登録支援機関です。
登録支援機関を活用することで、企業は煩雑な手続きをほぼ全て任せられるのです。
例えば、外国人労働者の入国に必要な書類作成や役所手続きへの同行も、登録支援機関が一括して対応してくれます。
細かな業務ではありますが、そういった業務に社内の人員を割く必要がなくなり、本業に集中できる環境を整えられるのは大きな魅力です。
さらに、言葉が通じない、文化が違う、日本のルールや習慣が分からない外国人労働者に対しても、登録支援機関が適切にサポートを行います。
また、住居の確保や生活オリエンテーションといった日常支援も代行します。
生活必需品の購入方法や交通機関の利用法、地域の医療機関の案内など、慣れない環境での外国人労働者の生活を支援するのも、登録支援機関のお仕事です。
登録支援機関を利用することで、現場で対応する社員の手間やトラブルのリスクが大幅に軽減させることが出来るようになります。
登録支援機関が行う代行業務一覧
| 業務内容 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 事前ガイダンスの実施 | 外国人労働者への就業内容、生活ルール、報酬条件などの説明 |
| 入国・出国時の支援 | 空港での出迎え、帰国時の空港までの送迎 |
| 住居確保のサポート | 賃貸物件の紹介、契約手続きへの同行 |
| 生活オリエンテーション | 交通ルール、医療機関の利用方法、生活必需品の購入方法などの案内 |
| 公的手続きの支援 | 住民登録、社会保険加入手続きの同行 |
| 日本語教育の提供 | 日本語教室の案内やオンライン教材の提供 |
| 相談窓口の設置 | 労働条件や生活に関する相談の対応 |
| 定期的な面談の実施 | 労働者の状況を確認し、行政への報告を行う |
| 転職支援(人員整理等の場合) | 離職後の新しい職場の紹介や就職活動の補助 |
登録支援機関が行う代行業務は、上記の表をご覧頂いてもわかるように、非常に幅が広く、受入企業に代わり外国人労働者の生活全般をサポートしてくれます。
表にもあるように入国時の送迎や生活オリエンテーションの実施、住居の確保、公的手続きへの同行など、外国人労働者が新しい環境に順応するための支援の、ほぼすべてを代行してくれます。
また、日本語教育の提供や相談窓口の設置も登録支援機関が行ってくれるため、外国人労働者は登録支援機関に対して安心感を持ち、日常生活や職場での不安を解消する相談相手として信頼を寄せることができます。
登録支援機関が行う外国人労働者への細かなケアと行政への報告
- 定期面談の実施: 外国人労働者の就労や生活の状況を把握するため、3か月に1回以上の面談を実施。
- 問題解決の支援: 職場や生活での困りごとを聞き取り、具体的な解決策を提案。
- 法令遵守の確認: 労働基準法や入管法に違反がないか確認し、必要に応じて行政に通報。
- 行政報告の徹底: 面談の結果を基に、行政に適切な報告を行い、信頼関係を構築。
- 企業と労働者のサポート: 労働者の満足度を向上させ、企業のリスク軽減と環境整備を支援。
登録支援機関は、外国人労働者の就労や生活の状況を把握するため、3か月に1回以上の定期面談を実施します。
登録支援機関が行う面談では、労働者が職場や日常生活で抱える問題を聞き取り、外国人労働者に対して、具体的なアドバイスなどを伝える場合があります。
例えば、外国人労働者が働く職場での業務内容に不満がある場合などは、受入企業に対して業務調整の提案を行うことも考えられます。
また、外国人ならではの生活面での困りごとについては、生活オリエンテーションや地域リソースの活用方法を案内します。
さらに、登録支援機関は、面談で得た情報を基に、労働基準法や入管法に違反がないかを確認します。
仮に受入企業に法令違反やトラブルの兆候があれば、適切な行政機関に迅速に報告することが義務付けられています。
長時間労働の問題が発覚した場合などには、登録支援機関は労働基準監督署にその事実を通報し、適切な是正措置を取るサポートをしなければなりません。
登録支援機関が行う「義務的支援」と「任意的支援」の違いとは?
支援カテゴリの比較
| カテゴリ | 義務的支援 | 任意的支援 |
|---|---|---|
| 対象 | 法律で実施が義務付けられている支援 | 法律上、実施が望ましいとされる支援 |
| 主な内容 |
|
|
| 実施の必要性 | 必ず実施しないと法令違反になる | 企業や労働者の状況に応じて柔軟に対応 |
| 目的 | 外国人労働者の生活安定と法令遵守の確保 | 労働者のさらなる定着率向上や満足度向上 |
| 企業への影響 | 義務を果たすことで罰則を回避 | 労働者の満足度向上や企業イメージの改善 |
登録支援機関が提供する支援は「義務的支援」と「任意的支援」の2つに分かれます。
「義務的支援」と「任意的支援」の違いは、法令で義務付けられているかどうかにあります。
義務的支援は、外国人労働者が日本での生活や就労を円滑に行うために必須とされる支援であり、登録支援機関はこれを確実に行う責任があります。
一方、任意的支援は法律で義務付けられていませんが、実施することで労働者の満足度や定着率を高める役割を果たします。
例えば、日本語学習の機会の提供に関しては、日本語能力試験の受験支援や日本語学習に要する費用の補助などです。
登録支援機関が行う「義務的支援」と「任意的支援」の違いとは?
義務的支援の具体例
- 事前ガイダンス
雇用契約を結んだ後、労働条件や入国手続きなどについて、対面またはリモートで説明。 - 出入国の送迎
日本に到着した際、空港から住居までの送迎や、帰国時の空港までの同行。 - 住居確保・生活に必要な契約のサポート
住居の確保、銀行口座開設、ライフラインの契約などの手続きサポート。 - 生活オリエンテーションの実施
労働者に日本の生活ルールや交通機関の利用方法を説明。 - 公的手続きへの同行
住民登録や社会保険加入の手続きをサポートします。 - 日本語学習の機会提供
日本語教室の案内、日本語学習教材の提供。 - 相談・苦情対応
外国人が理解できる言語で、職場や生活上の相談・苦情対応。 - 日本人との交流促進
地域で行われるイベントなど、日本人との交流の場を提供。 - 転職支援(人員整理等の場合)
企業の都合で解雇された場合など、転職活動のサポートを実施。 - 定期的な面談の実施
労働者の職場環境や生活状況を確認し、行政へ報告。
義務的支援は、特定技能外国人が日本での生活や就労を安心して行えるようにするための基本的な支援です。
例えば、生活オリエンテーションでは、労働者が日本での生活に早く馴染めるよう、交通ルールやゴミ出しのルールなど、地域特有の生活習慣を具体的に説明し、指導します。
他にも、交通機関の使い方や最寄りの医療機関、銀行の利用方法など、日常的に必要な情報も丁寧に教える必要があります。
また、公的手続きへの同行では、住民登録や健康保険の加入、銀行口座の開設など、手続きが複雑で言語の壁が大きい場面を登録支援機関がカバーしてくれます。
さらに、登録支援機関が行う定期的な面談では労働条件に関する問題や、同僚とのコミュニケーションの課題について相談を受け、企業と連携して解決を図るなどの業務を登録支援機関は「義務」として行う必要があるのです。
任意的支援とは?何をしてくれるの?
任意的支援の具体例
- 事前ガイダンスに関する任意的支援
入国から就業までの過程で外国人の身の回りに関する気になる事項についても、情報提供を行うことが望まれます。例えば以下のような事項です。
①日本の気候や適した服装
②本国から持参すべき物
③日本で初任給をもらうまでの当面の生活費の目安 - 日本語学習の機会の提供に関する任意的支援
①日本語能力試験の受験支援
②日本語学習に要する費用の補助 - 出入国する際の送迎
技能実習2号等から特定技能1号へ変更した外国人の送迎は、義務的支援に含まれませんが、事業所の判断で、送迎したり費用を負担したりすることができます。送迎をしないという場合には、交通手段や緊急時の連絡先を伝えておきます。
任意的支援は、外国人労働者が、より安心して日本で働ける環境を整えるために重要な役割を果たします。
このような支援を通じて、登録支援機関は外国人労働者が日本国内でのキャリアを途切れさせることなく、継続的に働ける環境を整えます。
登録支援機関になるための要件とは?どんな条件があるのか
要件と具体的条件
| 要件 | 具体的な条件 |
|---|---|
| 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること。(兼任も可能) | |
| 以下のいずれかに該当すること。 |
|
| 外国人が、十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること | |
| 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと | |
| 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと |
登録支援機関になるためには、一定の要件と条件を満たし、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければいけません。
また過去に法令違反や不正行為がないこと、財政基盤が安定していることが登録支援機関になるためには求められます。
外国人支援に関する知識や経験を有していない場合、適切な支援を提供することが難しくなるため、文化や言語の違いを理解し、迅速に対応できる外国語能力などのスキルが重要です。
そして「組織体制」も重要です。
外国人支援を担当するスタッフが適切に配置され、支援業務をスムーズに行える体制を整えているか、さらに「不適格事由の不存在」として、反社会的勢力との関与がないことや、過去に特定技能制度関連の法令違反をしていないことが条件として挙げられます。
最後に、「支援計画の作成能力」も必要です。
特定技能外国人が安心して働けるよう、入国から生活支援までを含む計画を適切に作成し、実施できることが求められます。
これらの要件を満たすことで、登録支援機関として信頼される存在となり、受入企業や労働者に貢献できます。
登録支援機関の月額相場費用と料金
| サービス内容 | 月額費用の相場 |
|---|---|
| 基本支援(義務的支援のみ) | 25,000~30,000円/人 |
| 任意的支援を含む総合支援 | 30,000~50,000円/人 |
| オプションサービス(日本語教育など) | 10,000~20,000円追加/人 |
| 特別対応(転職支援や個別相談対応) | 50,000円以上/人 |
登録支援機関を利用する際の月額費用は、サービス内容によって異なりますが、基本支援のみを提供する場合、月額25,000~30,000円が一般的な相場です。
基本支援の中には、義務的支援である「生活オリエンテーション」や「公的手続きの同行」「定期面談」などのサポートが含まれます。
一方、任意的支援を含む総合的なサポートを依頼する場合は月額30,000~50,000円程度が目安です。
任意的支援には、日本語教育の提供や地域交流の促進サポートなど、労働者の満足度を高める追加サービスが含まれます。
さらに、オプションサービスとして、日本語教育の提供や特別な相談対応を依頼する場合、基本的には追加で10,000~20,000円程度が必要になります。
弊社が提携している登録支援機関の中には日本語教育の提供を無料で行っているところもあります。
その他にも特別対応や転職支援などの個別対応を依頼する場合には、1人あたり50,000円以上の費用がかかることもあるそうです。
登録支援機関の適切な料金設定を見極める5つのポイント
- サービス内容の明確化: 提供される義務的・任意的支援の詳細を確認する。
- 追加費用の有無: 日本語教育や特別相談など、追加料金の有無を把握する。
- 支援の質と実績: 支援内容の質や、過去の実績を基に信頼性を確認する。
- 料金の相場との比較: 相場とかけ離れていないかを調査し、適正価格を判断する。
- カスタマイズの柔軟性: 自社のニーズに応じたサービスの調整が可能かを確認する。
登録支援機関の料金設定を見極める際には、まずサービス内容が明確であるかどうかを注意しましょう。
特に義務的支援と任意的支援の区別が明確に示され、それぞれの支援内容が具体的に記載されているかを確認してください。
また、日本語教育や特別相談など、追加費用が発生するサービスがある場合は、その有無や金額を事前に確認することもお忘れなく。
次に、支援の質と実績も重要なポイントです。
過去の利用者のレビューや実績を確認し、登録支援機関が信頼できるのか、また料金が一般的な相場と大きく異なっていないかも合わせて確認しましょう。
また、自社のニーズに合わせてサービスをカスタマイズできるかどうかも確認してください。
例えば、義務的支援のみが必要な場合や、特定の労働者への支援を強化したい場合に柔軟に対応してくれる機関を選ぶと良いでしょう。
これらのポイントを踏まえて適切な料金設定を見極めることで、企業に最適な登録支援機関を選び、コストパフォーマンスを最大化することができます。
登録支援機関のまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 登録支援機関の役割: 外国人労働者の入国手続きや生活支援を一括してサポートする重要な機関です。
- 義務的支援と任意的支援の違い: 法令で義務付けられた支援と、労働者の定着率向上を目的とした追加支援があります。
- 料金の相場: 月額25,000~50,000円程度が一般的で、サービス内容により異なります。
- 利用のメリット: 手続きの効率化、リソース削減、労働者との信頼関係構築が期待できます。
- 選び方のポイント: 費用、サービス内容、実績を確認し、企業ニーズに合った機関を選びましょう。
この記事では、登録支援機関の役割や料金相場、利用のメリットについて詳しく解説しました。
外国人労働者の受入れを成功させるためには、登録支援機関を上手に活用することが重要です。
特にミャンマーの優秀な人材を確保したい企業様は、ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関の『ミャンマー・ユニティ』にお申し付けください。弊社が提携させていただいている登録支援機関をご紹介させていただきます。
ミャンマー・ユニティは、送り出し機関としての豊富な実績を持ち、労働者と企業の双方に最適なサポートを提供しています。
外国人労働者の採用でお悩みの方は、ぜひミャンマー・ユニティにご相談ください!
無料でご提供しております