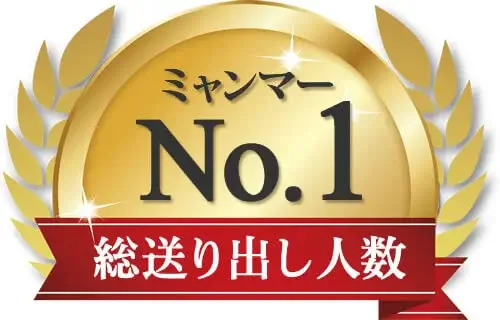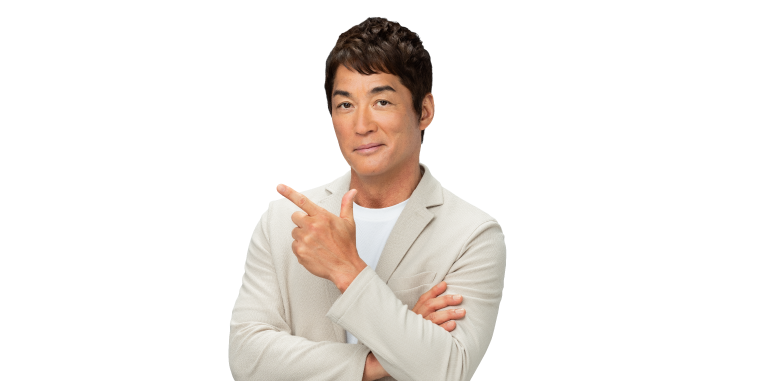特定技能『介護』とは?外国人労働者受け入れの制度と活用のポイント
介護分野での人材不足に直面していませんか?
特に介護分野での高齢化が進む中、優秀な人材の確保が課題となっている施設も多いかと思います。
そんな中、特定技能「介護」は、即戦力となる外国人材を受け入れることで、人手不足を防ぎ、安定した労働基盤を構築する有効な手段となります。
この記事では、特定技能「介護」の概要や制度の目的、活用のメリットについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

目次
特定技能「介護」とは何か?どういった制度なのか基本を解説
特定技能「介護」とは
- 制度の目的:深刻な人手不足に対応し、介護分野で即戦力となる外国人材を受け入れること。
- 対象分野:介護、外食、宿泊、農業、飲食料品製造など16分野が指定されている。
- 求められる技能水準:介護技能評価試験の合格
- 日本語能力:日本語能力試験N4以上あるいは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic A2)の合格、介護日本語評価試験の合格
- 在留期間:特定技能1号は最長5年間の在留が可能。
日本では、2025年には65歳以上の高齢者の人口が全体の約30%に、2040年には40%に達すると予測されており、介護サービスの需要が急増しています。
これに伴い、介護分野では深刻な人手不足が顕在化しています。
厚生労働省のデータによれば、介護職員の必要数は2025年までに約243万人に、2040年までに約280万人に達する見込みです。
しかし、現在の人材供給ペースでは2025年には約32万人が、2040年には約69万人が不足するとの推計が出されています。特に地方部では介護職員の確保が困難であり、施設やサービスの維持が危ぶまれるケースも見られます。
こうした状況を背景に、特定技能「介護」という在留資格が創設されました。
この制度は、即戦力となる外国人材を受け入れることで、現場の人手不足を緩和し、高齢者に必要なサービスを安定的に提供することを目的としています。
この制度により、各施設では質の高いケアを維持しながら、職員の負担軽減にも寄与すると期待されています。
特定技能「介護」の概要と基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 介護分野における深刻な人手不足を解消するため、即戦力となる外国人材を受け入れること。 |
| 対象業務 | 身体介護(入浴、食事、排せつの介助など)およびこれに付随する支援業務。※訪問系サービスは対象外。 |
| 必要な技能水準 | 介護技能評価試験の合格、または同等の知識・経験を有すること。 |
| 日本語能力要件 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」の合格が求められる。 |
| 在留期間 | 1年、6か月、または4か月ごとの更新で、通算で最長5年間の在留が可能。 |
特定技能「介護」は、日本の高齢化社会に伴う介護人材の不足を背景に創設された在留資格です。
この制度の目的は、介護分野で即戦力となる外国人材を受け入れることで、人手不足を解消し、質の高い介護サービスを提供することにあります。
特定技能「介護」の特徴として、身体介護業務(入浴、食事、排せつの介助など)およびこれに付随する支援業務が対象となりますが、訪問系サービスは現在のところ含まれませんが、2024年6月19日、厚生労働省は、これまで認められていなかった特定技能で働く外国人材の訪問介護において、解禁する方針を示しました。訪問介護・サ高住は2025年4月に解禁が予想されます。
また、特定技能「介護」では、介護技能評価試験の合格や同等の知識・経験が求められ、さらに業務遂行に必要な日本語能力も求められます。
特定技能「介護」で訪問介護が解禁された背景
近年、介護業界は深刻な人手不足に直面しています。厚生労働省の「訪問系サービスなどへの従事について」によれば、2022年度における施設介護職員の有効求人倍率は3.79倍でしたが、訪問介護員の有効求人倍率は15.53倍に達しています。
これらのデータから、介護業界全体に人手不足の問題があることは明らかですが、特に訪問介護分野での人手不足が非常に深刻であることが分かります。
また、同じ資料によれば、2040年には282,914人の訪問介護員が必要とされる見込みですが、2021年時点での訪問介護員数は250,728人に過ぎません。そのため、2040年までに約32,000人の訪問介護員を新たに確保する必要があります。
訪問介護を解禁する動きは、現在の状況に対応するとともに、将来的な深刻な人手不足を見据えたものであるといえるでしょう。
特定技能「介護」で求められる日本語能力とその理由
特定技能「介護」では、日本語能力試験N4以上、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格が求められます。
さらに、介護業務に必要な専門用語を理解するため、「介護日本語評価試験」の合格も必要です。
介護現場では、利用者の体調や要望を正しく理解し、適切に対応することが求められます。
また、緊急時には医師や看護師と迅速に連携を取る必要があります。
そのため、日常会話の能力だけでなく、専門用語や指示を正確に理解できる日本語能力が重要です。
このような背景から、日本語能力が特定技能「介護」において重要視されているのです。
特定技能制度の目的と対象分野
特定技能制度は、日本における深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
この制度は、以下の16の産業分野で適用されています。
| 介護 | ビルクリーニング | 工業製品製造 | 建設 | 造船・舶用工業 | 自動車整備 | 自動車運送業 | 鉄道 |
| 航空 | 宿泊 | 農業 | 漁業 | 林業 | 木材産業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
介護分野における外国人労働者が行える具体的な業務内容は多岐にわたります。
入浴、食事、排せつの介助といった基本的な身体介護だけでなく、利用者一人ひとりの状況に応じた個別ケアが含まれます。
例えば、入浴介助では安全に配慮しながら体を清潔に保つだけでなく、リラックス効果を高めるコミュニケーションが重要です。
また、食事介助では利用者の咀嚼や嚥下能力を見極めながら、適切な形態の食事を提供したり、レクリエーションの実施では、利用者の楽しみや生きがいを支える活動などが求められます。
また、機能訓練の補助では、理学療法士や作業療法士の指示を受けながら、外国人労働者が利用者の運動能力や生活動作の向上を目指す支援を行います。
特定技能「介護」でできること・できないことは?
| できること | できないこと |
|---|---|
| 入浴、食事、排せつの介助などの身体介護 | |
| レクリエーションの実施 | 医療行為(例:点滴、投薬) |
| 機能訓練の補助 | 介護計画の策定 |
| 生活援助(例:掃除、洗濯) | 施設の管理業務 |
特定技能「介護」で従事可能な業務には、身体介護やレクリエーション以外にも多岐にわたる内容があります。
例えば、生活援助として掃除や洗濯などの日常生活を支える業務も含まれますし、利用者が自立した生活を送れるよう、日常動作の練習をサポートする機能訓練の補助も業務範囲に含まれます。
また外国人労働者が理学療法士や作業療法士の指導のもと、利用者に適切な運動や動作訓練を提供することも業務として行うことが可能です。
一方で、外国人労働者が介護計画の策定や施設運営に関する管理業務を行うことはできません。
これらは専門的な知識や現場全体の把握が必要な業務であり、2025年現在の日本の基準では資格を持った専門職が担当しなければなりません。
さらに、医療行為も従事不可です。
点滴や投薬などの行為は、医師や看護師といった資格保持者のみが行えるため、注意が必要です(これは日本人も同じ)。
外国人労働者の就労時間や残業については、日本の労働基準法に基づき、適正な範囲内での管理が求められます。
特定技能「介護」での就労条件と給与体系や福利厚生について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定技能1号(介護分野) |
| 在留期間 | 1年、6か月、または4か月ごとの更新。通算で上限5年まで。 |
| 技能水準 | 介護技能評価試験に合格、または介護職種の技能実習2号を修了。 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認。具体的には、国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上の合格が必要。 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない。 |
| 支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要。 |
| 雇用形態 | 直接雇用が原則。 |
| 従事可能業務 | 身体介護(入浴、食事、排せつの介助等)、レクリエーションの実施、機能訓練の補助など。訪問系サービスは対象外。 |
| 給与体系 | 日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められる。 |
| 福利厚生 | 日本人労働者と同等の待遇を提供する必要がある。 |
特定技能「介護」の在留資格は、介護技能評価試験に合格するか、介護職種の技能実習2号を修了した外国人が対象となります。
また、業務に必要な日本語能力として、国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上の合格が求められます。
特定技能1号は即戦力としての就労を目的としており、在留期間が最長5年に限定されています。そのため、安定した長期滞在を前提とする家族の帯同は基本的に認められていません。
雇用形態に関しては直接雇用が原則であり、派遣などの形態は認められていません。
給与体系については、日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められ、福利厚生も日本人労働者と同等の待遇を提供する必要があります。
これらの条件を満たすことで、外国人労働者が安心して働ける環境を整え、介護現場の人手不足解消に寄与することが期待されています。
特定技能介護の雇用形態のルールと制約
| 項目 | ルール・制約 |
|---|---|
| 雇用契約形態 | 直接雇用が原則。派遣雇用は認められない。 |
| 報酬額 | 日本人と同等以上の水準を保証する必要がある。 |
| 労働時間 | 1日8時間、週40時間を上限とし、残業には36協定の締結が必要。 |
| 残業手当 | 割増賃金の支払いが義務付けられている。 |
| 支援体制 | 生活オリエンテーション、日本語学習の支援、相談窓口の設置などが必要。 |
特定技能「介護」の雇用形態に関するルールは、上記の表が参考になるでしょう。
まず、特定技能「介護」における雇用契約は直接雇用が原則となります。派遣形態での雇用は認められていません。
次に、報酬額については、外国人労働者が不当な低賃金で働かされることを防ぐために、日本人と同等以上の水準を保証するように定められています。
外国人労働者の労働時間や残業に関しても、日本の労働基準法が適用されます。
1日の労働時間は原則8時間、週40時間を超えてはなりません。残業を行う場合は、労使協定(36協定)の締結が必要であり、割増賃金の支払いも義務付けられています。
さらに、受入れ機関は、外国人労働者に対して適切な支援体制を整える義務があります。
受入れ機関が行うべき外国人労働者に対する支援体制
| 支援内容 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 生活オリエンテーションの実施 | 日本の生活習慣やルール、交通機関の利用方法、医療機関の受診方法などを説明します。 |
| 住居の確保・生活に必要な契約支援 | 適切な住居の提供や、電気・ガス・水道などのライフライン契約をサポートします。 |
| 日本語学習の機会提供 | 業務や日常生活で必要な日本語能力向上のため、学習機会を提供します。 |
| 相談・苦情対応 | 労働者が直面する問題や悩みを相談できる窓口を設置し、適切に対応します。 |
| 社会保険手続きの支援 | 健康保険や年金など、社会保険の加入手続きをサポートします。 |
| 日常生活や行政手続の支援 | 銀行口座の開設や携帯電話の契約、在留資格の更新手続きなどを支援します。 |
特定技能「介護」分野で外国人労働者を受け入れる際、受入れ機関には上記の表の支援体制の整備が求められます。
受入れ機関は、これらの支援を自社で実施するか、または登録支援機関に委託することが可能です。
例えば、生活オリエンテーションでは、地域の生活情報や緊急時の対応方法を詳しく説明することが重要です。
日本語学習の機会提供では、業務に必要な専門用語や敬語の使い方などを教え、実務に直結する内容を含めると効果的です。
さらに、相談・苦情対応の窓口を設置することで、労働者の不安や問題を早期に解決し、職場環境の改善につなげることができます。
これらの支援体制を整えることは、外国人労働者の円滑な就労と生活をサポートし、受入れ機関としての信頼性を高めるために不可欠です。
特定技能介護の退職と転職のルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 退職時の手続き |
・受入れ機関は、退職日の翌日から14日以内に「特定技能所属機関等に関する届出」を提出する義務がある。 ・特定技能外国人本人も、14日以内に同様の届出を行う必要がある。 |
| 転職可能な分野 | 転職先も介護分野に限られる。 |
| 転職時の条件 |
・新たな受入れ機関は出入国在留管理庁の基準を満たす必要がある。 ・外国人支援体制が整備されていることが条件。 |
| 在留期間への影響 |
・頻繁な転職や長期間の無職期間は在留資格の更新に影響を与える可能性がある。 ・継続的な就労状況が審査の対象となる。 |
特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人労働者が退職や転職を行う際には、上記の表のようなルールと制約があります。
まず、退職する場合、受入れ機関は出入国在留管理庁に対して、退職日の翌日から起算して14日以内に「特定技能所属機関等に関する届出」を提出する義務があります。
同様に、特定技能外国人本人も、退職後14日以内に「特定技能所属機関等に関する届出」を行う必要があります。
外国人労働者が転職を希望する場合、特定技能「介護」の在留資格は、特定の分野での就労を前提としているため、新たな就職先も介護分野でなければならないというルールがあります。
外国人労働者の転職先になる、新しい受入れ機関は、出入国在留管理庁の基準を満たす必要があり、例えば、適切な雇用契約の締結や外国人支援体制の整備が求められます。
転職後も、受入れ機関と外国人本人の双方が、所定の届出を行うことが義務付けられています。
さらに、外国人労働者の在留期間の更新時には、継続的な就労状況や生活状況が審査されます。
頻繁な転職や長期間の無職期間は、在留資格の更新に影響を及ぼす可能性があり、避けるべきでしょう。
特定技能2号が介護職だけは認められていない
特定技能1号での外国人の就労は5年しか認められておらず、5年を超えて働くには特定技能2号の資格取得が必要です。特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められています。特定技能1号では企業が支援計画を策定し、生活や業務のサポートを行う義務がありますが、2号ではこの義務がなくなります。これにより、外国人労働者が自主的に生活を送ることが前提となります。
しかしながら、日本政府は特定技能許可12職種の中で、介護職だけには特定技能2号を認めていません。
介護職だけは外国人にとって超難関である「介護福祉士」試験合格者にのみ、5年を超えて働く許可を与えています。
特定技能1号の介護福祉士資格取得プロセスについて
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 実務経験の積み重ね | 特定技能1号の在留資格で、介護現場で3年以上の実務経験を積む必要があります。 |
| 2. 実務者研修の修了 | 介護福祉士国家試験を受験するためには、厚生労働省認定の実務者研修を修了することが必須です。 |
| 3. 介護福祉士国家試験の受験 | 国家試験は毎年1回実施されます。筆記試験は日本語で行われるため、日本語能力が重要です。 |
| 4. 資格取得後の手続き | 介護福祉士資格を取得すると、在留資格を「介護」に変更でき、無期限での就労が可能になります。 |
特定技能1号で介護分野に従事する外国人労働者は、介護福祉士資格を取得するために上記のステップを踏む必要があります。
まず、介護現場で3年以上の実務経験を積むことが第一条件となります。
この期間中に業務で必要な知識や技能を習得し、職場での信頼関係を築きます。
次に、介護福祉士国家試験を受験するためには、厚生労働省認定の「実務者研修」を修了することが必須です。
国家試験は毎年1回、日本語で実施されており、試験内容は専門知識に加えて、法規や倫理に関する問題も含まれるため、高い日本語能力が求められます。
そして、資格取得後は、在留資格を「介護」に変更する手続きを行うことで、無期限での就労が可能になります。
また、この資格により家族の帯同も認められるため、外国人労働者の長期的なキャリアパスを支援するうえで、施設側の協力が重要です。
資格取得のための学習環境や情報提供を行うことで、労働者の成長と職場の質の向上が期待されます。
試験に合格できなかった場合はどうなる?
特定技能1号の在留資格で介護分野に従事する外国人労働者が、介護福祉士国家試験に不合格となった場合、再受験の機会はありますが、いくつかの制約が存在します。
まず、介護技能評価試験および介護日本語評価試験に不合格となった場合、再受験までに45日間の待機期間が設けられています。
この期間中は再受験ができません。
また、特定技能1号の在留期間は最長で5年間と定められており、この期間内に介護福祉士の資格を取得できない場合、在留資格の更新や変更が難しくなる可能性があります。
雇用主としては、外国人労働者が試験に合格できるよう、以下のサポートが求められます。
- 学習支援:試験対策のための教材提供や勉強時間の確保。
- 日本語能力向上支援:日本語研修の実施やコミュニケーションの機会提供。
- メンタルサポート:試験への不安やプレッシャーに対する相談窓口の設置。
これらの支援を通じて、外国人労働者が介護福祉士資格を取得し、長期的に日本で活躍できる環境を整えることが、雇用主の責務と言えるでしょう。
まとめ:特定技能「介護」に関する重要なポイント
- 制度の目的
特定技能「介護」は、介護分野での人手不足を解消し、即戦力となる外国人労働者を受け入れるために設けられた制度です。 - 従事可能な業務範囲
身体介護(入浴、食事、排せつの介助など)やレクリエーションの実施、機能訓練の補助が含まれます。 - 在留資格と更新要件
特定技能1号では最長5年の在留が可能ですが、介護福祉士資格を取得することで、無期限の在留資格「介護」に変更できます。 - 日本語能力の重要性
日本語能力試験N4以上や「介護日本語評価試験」の合格が必要です。これは利用者や医療関係者との正確なコミュニケーションが求められるためです。
この記事では、特定技能「介護」に関する制度や資格取得のプロセス、労働条件について詳しく解説しました。
外国人労働者を適切に受け入れ、長期的な人材確保を実現するためには、信頼できる送り出し機関との連携が不可欠です。
ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関の『ミャンマー・ユニティ』では、優れたミャンマー人材の採用をトータルでサポートしています。また、弊社では829名の介護技能実習生、527名の介護特定技能生と世界最大級の介護職送り出し実績がございます。(2025年2月7日時点)
介護業務に必要なスキルや日本語能力を備えた人材を提供し、受入企業のニーズに合わせて柔軟なサポートを行います。
気になる方は、ぜひミャンマー・ユニティにご相談ください。
最適な外国人人材確保への第一歩を、ぜひミャンマー・ユニティで始めてみませんか?
無料でご提供しております