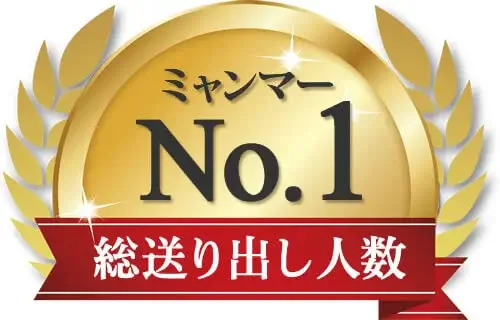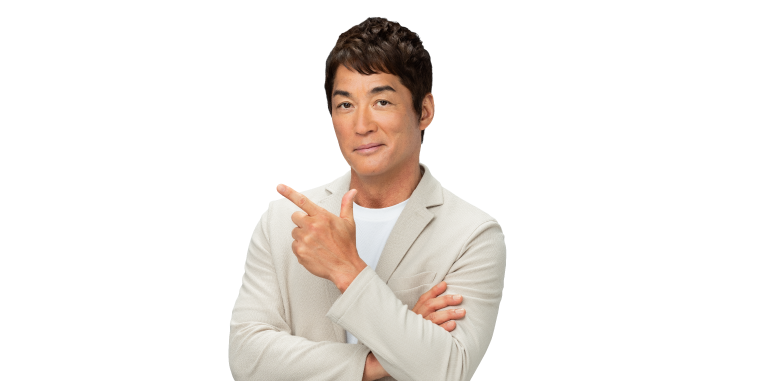特定技能制度とは?基本から手続き、令和6年の制度改善について徹底解説
深刻な人手不足に直面している企業にとって、優秀な外国人労働者の確保は大きな課題です。
特定技能制度は、即戦力となる外国人材を受け入れるための仕組みとして、多くの企業に利用されています。
しかし、手続きの流れや要件が複雑で、どのように始めればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定技能制度の基本情報から、手続きや必要書類、実際の活用方法に関して詳しく解説しています。
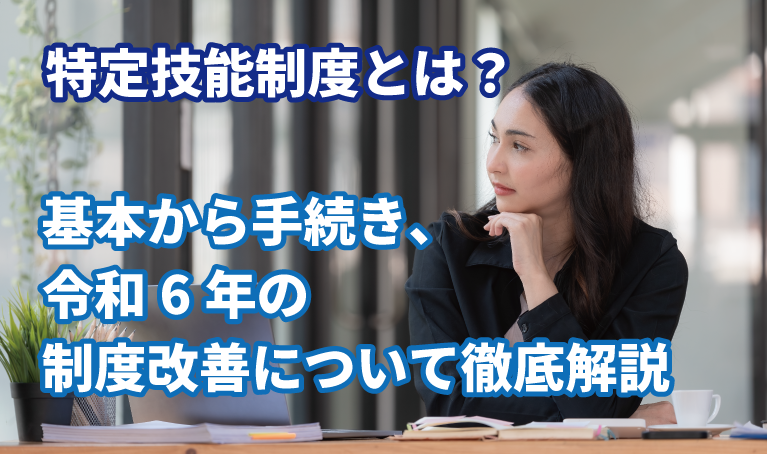
目次
在留カード「就労不可」の意味とは
特定技能制度の概要について
- 目的: 深刻な人手不足に対応し、特定の産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるための制度。
- 在留資格の種類: 特定技能1号(基礎的な技能)と特定技能2号(熟練技能)の2種類がある。
- 受け入れ分野: 外食、介護、宿泊、農業、飲食料品製造業など16の特定産業分野が対象。
- 在留期間: 特定技能1号は、1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。特定技能2号は3年、1年又は6か月ごとの更新。
- 日本語能力要件: 特定技能1号では、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
特定技能制度は、2019年4月に開始された日本の在留資格制度です。
主に、人手不足が深刻な16の特定産業分野で働く外国人を受け入れる仕組みとして設けられました。
この制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類があり、それぞれ求められる技能や在留可能な期間が異なります。
特定技能1号では、一定の知識や経験が必要とされ、在留期間は最長5年です。
一方、特定技能2号では熟練技能が求められ、在留期間の制限がありません。
この制度では、基本的な日本語能力や業務関連スキルを試験で確認します。外国人労働者をスムーズに受け入れるため、受け入れ機関や登録支援機関の支援も必須です。
特定技能制度設立の背景と目的
日本では、少子高齢化の進行に伴い、労働力不足が深刻な課題となっています。
特に、2025年には「団塊の世代」の多くが75歳以上の後期高齢者となり、労働力人口の減少が一層顕著になると予測されています。
このような状況下で、企業は人手不足が業績拡大の大きな障害となっており、特にサービス業や製造業など多くの業種で人材確保が困難となっています。
この深刻な人手不足に対応するため、政府は2019年4月に「特定技能制度」を導入しました。
この制度は、即戦力となる外国人労働者を受け入れることで、特定の産業分野における人材不足を補い、日本経済の持続的な成長を支えることを目的としています。
外食、介護、宿泊、農業、飲食料品製造業など16の産業分野が対象となっており、これらの分野で一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる仕組みとなっています。
2025年現在、特定技能制度は多くの企業で活用されており、外国人労働者の受け入れが進んでいます。
特定技能制度の対象となる外国人労働者は?
| 在留資格 | 対象者の特徴 | 主な受け入れ分野 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 |
・相当程度の知識または経験を持つ ・試験で技能水準と日本語能力を確認 ・家族の帯同は認められない |
・外食 ・介護 ・宿泊 ・農業 ・飲食料品製造業 (全16分野) |
| 特定技能2号 |
・熟練した技能を持つ ・試験で技能水準を確認(日本語試験は不要(分野によってはある)) ・家族の帯同が可能 |
・外食 ・宿泊 ・農業 ・飲食料品製造 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・漁業 |
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消するために創設された制度です。
対象となる外国人労働者は、特定技能1号と2号に分かれます。
特定技能1号では、実務が可能な相当程度の知識や経験を持つ労働者が対象となっています。
特定技能1号は、介護や外食業など16分野における即戦力の活用が進められています。
一方、特定技能2号では熟練した技能が求められ、外食や宿泊といった11の分野での採用が行われています。
特定技能1号では、基本的な日本語能力や技能試験の合格が条件となっています。
なお、特定技能2号では、日本語能力試験は不要(分野によってはある)ですが、熟練技能を持つことで高い専門性を発揮できることが期待されています。
現在、多くの企業がこの制度を活用し、特に人手不足が深刻な分野での労働力補充に成功しています。
【令和6年】
特定技能制度の改正内容と具体的な変更点
| 改正内容 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| 対象分野の拡大 | 特定技能2号の対象分野に、工業製品製造業分野を含む全11分野を追加。 | 熟練した技能を持つ外国人材の活躍の場を広げ、製造業の人手不足を解消するため。 |
| 業務区分の統合 | 製造業分野の業務区分を10区分から3区分に統合し、柔軟な業務従事を可能に。 | 外国人材が幅広い業務に従事できるようにし、企業の運用負担を軽減するため。 |
| 受入れ機関の要件強化 | 繊維業において、適正な取引推進のため追加要件を設定。 | 労働環境の適正化と外国人材の保護を強化するため。 |
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に導入されました。
その後、労働市場の状況や産業界のニーズに応じて、制度の見直しと改正が行われています。
令和6年度の主な改正点として、まず、特定技能2号の対象分野の拡大が挙げられます。
改正後、工業製品製造業分野を含む全11分野で、熟練した技能を持つ外国人材の受け入れが可能となりました。
次に、製造業分野における業務区分の統合が実施されました。
従来製造業分野では10の業務区分が存在していましたが、これを3区分に統合することで、外国人材が幅広い業務に従事できるようになりました。そして、2024年3月29日に政府は分野名を「工場製品製造業分野」と変更したうえで、新たな業種・業務区分を追加する閣議決定を行いました。
さらに、受入れ機関の要件強化も行われ、繊維業においては、労働環境の適正化と外国人材の保護を強化するため、追加の要件が設定されることになりました。
これらの改正は、特定技能制度の柔軟性と適用範囲を拡大し、外国人材の受け入れを促進する一方で、労働環境の適正化と外国人材の保護を強化することを目的としています。
出典:経済産業省対象分野の拡大について、何がどう変わったの?
変更点・改善点・注意点
- 変更点: 特定技能2号の対象分野に、工業製品製造業分野を含む全11分野が追加されました。
- 改善点: これにより、熟練した技能を持つ外国人材の活躍の場が広がり、製造業の人手不足解消が期待されています。
- 注意点: 新たに追加された分野では、特定技能2号の受け入れ開始時期や具体的な手続きについて、最新情報の確認が必要です。
日本では、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化しています。特に製造業では、国内人材の確保が難しく、生産性向上の取り組みを行ってもなお人材不足が課題となっていました。
このような背景から、政府は特定技能2号の対象分野を拡大することを決定しました。
以前は、特定技能2号の対象分野は限られており、熟練した技能を持つ外国人材の受け入れが制約されていましたが今回の拡大により、新たな分野でも特定技能2号としての受け入れが可能となり、熟練工やマネジメント層としての外国人材の活躍が期待されています。
ただし、特定技能2号としての受け入れ開始時期については、今後規定類を調整の上、決まり次第公表される予定です。
業務区分の統合で、どんなことが出来るようになった?
変更点・改善点・注意点
- 変更点: 製造業分野の業務区分が19区分から3区分に統合されました。
- 改善点: 外国人材が幅広い業務に従事できるようになり、企業の運用負担が軽減されました。
- 注意点: 新たな業務区分に対応した試験制度の詳細について、最新情報の確認が必要です。
日本の製造業界では、中小企業を中心に人手不足が顕著で、生産性の維持・向上が求められている状況にあります。
そういった背景もあり、政府は製造業分野の業務区分を従来の19区分から3区分に統合しました。
具体的には、以下のように統合が行われました。
- 機械金属加工区分: 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装などの業務が含まれます。
- 電気電子機器組立て区分: 電気機器組立て、電子機器組立てなどの業務が含まれます。
- 金属表面処理区分: めっき、アルマイト、塗装などの業務が含まれます。
上記のような業務区分の統合により、外国人労働者はより幅広い業務に柔軟に従事できるようになりました。
外国人労働者が従事可能な業務は、以前は専門性が細分化され、例えば鋳造や鍛造などの個別の作業ごとに資格が必要でした。
しかし、統合後は、「機械金属加工区分」内であれば複数の業務を横断して行うことが可能になりました。
この改正により、外国人労働者に対しての業務の割り振りを企業側が柔軟に行えるようになり、生産性の向上が期待されています。
また、外国人労働者にとっても多様なスキルを習得する機会が増え、キャリアの幅が広がる利点があります。
受入れ機関の要件強化で、何が、どう変わったの?
変更点・改善点・注意点
- 変更点: 繊維業が特定技能制度の対象業種に追加され、受入れ機関に対して適正な取引推進のための追加要件が設定されました。
- 改善点: これにより、労働環境の適正化と外国人材の保護が強化され、業界全体の健全な発展が期待されています。
- 注意点: 受入れ機関は新たな要件を満たす必要があり、適切な労働条件の提供や法令遵守が求められます。
日本の繊維業界も他の業界と同じく、少子高齢化や若年層の就業者減少に伴い、深刻な人手不足が課題となっていました。
この状況を受け、政府は2024年9月4日に繊維業を特定技能制度の対象業種に追加することを決定しました。
しかし、過去に技能実習制度において、繊維業界では賃金未払いなどの不適切な事例が報告されており、外国人労働者の労働環境改善が急務とされていました。
このため、特定技能制度における繊維業の受入れに際しては、以下のような追加要件が設定されました。
- 適正な労働条件の確保: 受入れ機関は、外国人労働者に対し、日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
- 法令遵守の徹底: 労働基準法や最低賃金法など、関連法令を遵守し、過去に重大な違反がないことが求められます。
- 生活支援の充実: 外国人労働者が円滑に生活できるよう、住居の確保や日本語教育の提供など、生活支援体制の整備が必要です。
これらの要件強化により、受入れ機関は適切な労働環境を提供し、外国人労働者の権利保護を徹底することが求められるようになりました。
外国人労働者への改正の影響と雇用主の責任
特定技能制度の改正により、外国人労働者は従来以上に幅広い業務に柔軟に従事できるようになりました。
例えば、業務区分の統合により、以前は限定的だった作業範囲が拡大し、機械金属加工分野内で多様なスキルを活用することが可能となっています。
これにより、外国人労働者は多様な経験を積みやすくなり、キャリア形成の機会が広がります。
また、繊維業が新たに対象分野に追加されることで、これまで受け入れが難しかった分野でも活躍の場が提供されるようになりました。
同時に、適正な労働条件の確保が義務付けられたため、外国人労働者の権利が一層保護されるようになっています。
改正によって追加されたた雇用主側の注意点
企業や雇用主は、改正された制度を適切に運用する責任を負います。
具体的には、新たに定められた受入れ機関の要件を満たし、外国人労働者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められます。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 適正な労働条件の確保 |
・外国人労働者に日本人と同等以上の報酬を支払う。 ・労働契約に関する重要事項を外国人が理解できる言語で説明する。 |
| 法令遵守の徹底 |
・労働基準法や最低賃金法などの関連法令を遵守する。 ・過去に重大な法令違反がないこと。 |
| 生活支援体制の整備 |
・外国人労働者が生活に困らないよう住居を確保する。 ・日本語教育や生活オリエンテーションを提供する。 |
| 報告・届出義務 |
・受入れ状況や労働条件の変更を出入国在留管理庁に報告する。 ・外国人労働者の状況を適切に管理し、問題発生時に迅速に対応する。 |
上記の表のように、法令遵守を徹底し、労働基準法や最低賃金法に違反しないよう注意が必要です。
さらに、外国人労働者が職場や生活環境に円滑に適応できるよう、支援体制を充実させることも企業側に求められています。
その中には外国人労働者の住居の確保や日本語教育の提供、生活支援体制の整備なども含まれており、これらの取り組みは、外国人労働者の定着率向上と、企業全体の生産性向上に寄与するでしょう。
【1号・2号】
特定技能で働ける職種と求められる資格
| 区分 | 働ける職種 | 求められる資格 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 |
・外食 ・介護 ・宿泊 ・農業 ・飲食料品製造など16分野 |
・技能試験合格(例:介護技能評価試験) ・日本語能力試験N4以上 ・技能実習2号修了者は試験免除 |
| 特定技能2号 |
・外食 ・宿泊 ・農業 ・飲食料品製造業 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・漁業 |
・熟練技能を証明する試験合格 ・日本語能力試験不要 ・技能実習2号修了者は試験免除 |
特定技能制度には、特定技能1号と2号の2つがあり、それぞれ働ける職種や求められる資格が異なります。
特定技能1号では、介護や建設、宿泊など16分野が対象となります。
これらの分野では、日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(介護職種は介護日本語評価試験も必要)の合格や技能試験の合格が必須です。
また、技能実習2号を修了している場合のみ、試験が免除されます。
一方、特定技能2号は外食や宿泊、飲食料品製造業など11分野が対象です。この区分では、熟練技能が求められ、日本語能力試験は不要(分野によってはある)です。
しかし、技能試験の合格が必要である点は1号と共通しています。
雇用主は、外国人労働者が必要な資格を有しているかどうかを確認する責任があります。
また、特定技能2号では、家族帯同が可能であるため、受け入れ時の生活支援も求められます。
特定技能1号と2号の主な対象職種とその特徴
特定技能制度は、労働力不足が深刻な日本の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みです。
特定技能1号の対象職種は外食、介護、宿泊、農業、飲食料品製造など16分野です。この区分では、基礎的な技能と日本語能力を試験で確認します。
受け入れ期間は通算5年までで、特定技能1号は家族帯同は認められていません。これにより、短期間での即戦力確保を目的としています。
一方、特定技能2号は外食や宿泊、飲食料品製造業など11分野が対象となります。
特定技能2号は熟練技能が求められますが、日本語能力試験は不要(分野によってはある)です。
さらに、特定技能2号は家族帯同が可能であり、在留期間に制限がありません。
そういった制度上の違いから、特定技能2号は長期的に専門技能を活用することが可能です。
雇用主にとって重要なポイントは、各区分で求められるスキル水準と受け入れ期間の違いです。
また、特定技能2号では家族帯同が可能なため、生活支援体制の整備がより一層必要になります。
特定技能1号と2号に必要とされる資格取得のための試験やトレーニング
| 区分 | 資格取得に必要な試験 | トレーニング内容 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 |
・技能試験(例:介護技能評価試験、宿泊業技能測定試験) ・日本語能力試験N4以上 ・技能実習2号修了者は試験免除 |
・業務に必要な基礎的な技能訓練 ・日本語能力向上のための学習 ・特定分野の試験対策研修 |
| 特定技能2号 |
・熟練技能を証明する試験(例:建設分野特定技能評価試験) ・日本語能力試験は不要 ・技能実習2号修了者は試験免除 |
・業務に必要な高度な技能訓練 ・安全管理やリーダーシップ研修 ・資格更新に伴う専門スキル向上プログラム |
特定技能1号と2号では、資格取得のために求められる試験やトレーニングの内容が異なります。
特定技能1号では、技能試験や日本語能力試験N4以上の合格が基本的な条件です。
ただし、技能実習2号を良好に修了している場合、同職種での特定技能での就労であればこれらの試験が免除されます。
特定技能1号において受講が推奨されるトレーニング内容
| 対象分野 | トレーニング内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 介護 |
・身体介助の基本スキル ・利用者との適切なコミュニケーション方法 ・医療器具の基本的な取り扱い |
・ベッドから車いすへの移乗 ・食事介助や入浴支援 ・利用者の体調観察と報告 |
| 宿泊 |
・接客スキルの習得 ・宿泊施設のサービス提供の基礎 ・異文化対応のトレーニング |
・フロントでのチェックイン対応 ・客室清掃の手順 ・観光案内の提供 |
| 外食業 |
・飲食物調理の基礎 ・顧客対応スキル ・衛生管理の知識 |
・メニューに基づいた料理の調理 ・接客時の挨拶や注文の取り方 ・キッチンの衛生チェックと清掃 |
| 農業 |
・栽培管理の基礎 ・農産物の収穫・選別スキル ・農業機械の簡単な操作 |
・野菜や果物の収穫作業 ・出荷前の選別と梱包 ・トラクターの運転訓練 |
| 建設 |
・基本的な作業安全の知識 ・特定作業に必要な技術 ・現場でのコミュニケーションスキル |
・足場の設置と撤去 ・建設用資材の搬入 ・作業前の安全確認 |
特定技能1号のトレーニングでは、基礎的な技能や日本語能力の向上に重点を置いていただき、職場での円滑なコミュニケーションと業務遂行を支援する教育を実施することが推奨されます。
また対象分野ごとに定められた業務内容に即した技能訓練の実施が推奨されます。例えば、介護分野では身体介助の基本スキルや利用者との適切な対応方法、宿泊分野では接客やサービス提供の基礎を教えることが推奨されます。
特定技能2号において推奨されるトレーニング内容
| 対象分野 | トレーニング内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 建設 |
・施工管理技術の習得 ・安全基準遵守の具体的な手法 ・高度な作業計画と実行スキル |
・建築構造物の品質管理 ・現場の安全巡回とチェック ・資材の適切な使用計画の立案 |
| 造船・舶用工業 |
・高度な溶接技術の習得 ・精密な設備の組立スキル ・船舶設備の保守・修理技術 |
・大型船舶の溶接作業 ・舶用エンジンの組み立て ・船舶機器の定期点検と修理 |
| リーダーシップ研修 |
・チーム運営の効率化 ・トラブル対応力の向上 ・職場環境の改善スキル |
・現場での作業スケジュール管理 ・スタッフ間の役割分担の最適化 ・緊急時の迅速な対応策の実施 |
一方、特定技能2号では、熟練技能を証明する試験が必要ですが、日本語能力試験は不要です。
特定技能2号のトレーニングでは、高度な専門スキルの習得に加え、安全管理やリーダーシップ研修を行うことが推奨されます。
このトレーニングは、特定技能1号に比べてより専門性が高く、実践的な内容となります。
例えば、建設分野では、大規模な工事現場で必要な施工管理技術や、安全基準を守るための具体的な手法の指導が推奨されます。
造船・舶用工業分野では、高度な溶接技術や精密な設備の組立スキルを習得することが推奨されます。
さらに、リーダーシップ研修では、チームの効率的な運営方法や、トラブル発生時の適切な対応力を養う研修が推奨されます。
特定技能制度の手続き:申請から取得までの流れを徹底解説
| 手続きのステップ | 具体的な内容 | 関係者 |
|---|---|---|
| 1. 労働者の選定 |
・対象分野に合った外国人労働者を選定 ・必要な技能試験や日本語試験に合格済みであることを確認 |
・雇用主 ・外国人労働者 ・送り出し機関 |
| 2. 雇用契約の締結 |
・労働条件や報酬を日本人と同等以上に設定 ・契約内容を外国人労働者が理解できる言語で提供 |
・雇用主 ・外国人労働者 |
| 3. 在留資格の申請 |
・在留資格認定証明書の交付申請を出入国在留管理庁へ提出 ・必要書類を正確に準備 |
・雇用主 ・出入国在留管理庁 |
| 4. 入国および受入れ準備 |
・査証(ビザ)発給後、外国人労働者を日本に招聘 ・住居確保や生活オリエンテーションを実施 |
・雇用主 ・外国人労働者 ・登録支援機関 |
| 5. 就労開始 |
・雇用契約に基づく業務を開始 ・定期的なサポートやスキルアップ研修を提供 |
・雇用主 ・外国人労働者 |
特定技能制度の手続きは、上記の表のようになっています。
まず最初に、雇用主は対象分野に合致する外国人労働者を選定。
労働者が必要な技能試験や日本語能力試験に合格していることを確認し、その後、労働条件を明確にし、日本人と同等以上の報酬を提示したうえで雇用契約を締結します。
次に、在留資格認定証明書の申請を出入国在留管理庁へ提出。
この際に労働契約書や支援計画書などの必要書類を用意し、査証が日本の在外公館(大使館や領事館)から発行されます。
査証発給後、外国人労働者は正式に入国手続きを進めることができます。
査証が発給されると、労働者を日本に迎える準備を進めます。
住む場所を用意したり、生活に必要な情報を説明するオリエンテーションを行います。
これらの手続きは、登録支援機関と協力することでスムーズに進めることができます。
上記の手続きがすべて終わったあとに、外国人労働者の就労が開始可能になります。
ただし、この後も雇用主には、定期的なサポートやスキルアップのための研修提供が必要です。
ミャンマー人労働者受入の場合には上記の手続き以外にも「スマートカード」が必須となります。以下のリンクよりわかりやすく解説しております。
特定技能制度の手続きで必要になる書類一覧
| 書類名 | 内容 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 労働契約書 |
・労働条件を明記(雇用形態、報酬額、勤務時間など) ・外国人労働者が理解できる言語で作成 |
・雇用主が作成し、外国人労働者と双方で署名 ・専門家(社労士など)の確認を推奨 |
| 支援計画書 |
・生活や業務適応の支援内容を記載 ・住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習など |
・雇用主が作成 ・登録支援機関と協力して作成することも可能 |
| 在留資格認定証明書申請書 |
・外国人が特定技能として在留するための基本申請書 ・技能試験や日本語試験の合格証明を添付 |
・出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード ・必要事項を記入し、申請 |
| 技能試験合格証明書 |
・特定分野における技能の水準を証明 ・試験免除者は該当書類が不要 |
・試験実施機関から発行 ・技能実習2号修了者は修了証明書を使用可能 |
| 日本語能力試験合格証明書 |
・日本語能力試験N4以上の合格を証明 ・一部分野では不要 |
・試験実施機関(例:国際交流基金)から発行 ・技能実習2号修了者は免除 |
特定技能制度の手続きでは、上記の表の書類を準備する必要があります。
雇用主は、まず労働契約書を作成します。
この契約書には、雇用形態や報酬額などの条件を明記し、外国人労働者が理解できる言語で記載することが求められます(日本語のみはNG)。
また、支援計画書では、住居の確保や日本語教育など、外国人労働者への具体的な支援内容を詳細に記載しましょう。
支援計画書の作成には、登録支援機関の協力を得るとスムーズに進みます。
次に、在留資格認定証明書申請書を出入国在留管理庁に提出します。
この際に雇用する外国人労働者の技能試験や日本語試験の合格証明書も添付しなければなりません。
これらの証明書は、各分野の試験を実施する公的または認定された機関から発行されます。
例えば、介護分野では「介護技能評価試験」の運営機関が該当し、日本語試験では「国際交流基金」や「日本国際教育支援協会」が試験を担当します。
なお、技能実習2号修了者は一部試験が免除されるため、修了証明書を用意すれば、その後の手続きはスムーズに進められます。
修了証明書は技能実習を実施した機関が発行します。
これにより、追加の試験を受ける負担が軽減され、在留資格認定証明書の申請に必要な書類が簡略化されます。
特定技能制度のまとめ
理解してほしい5つのポイント
- 特定技能制度の目的: 日本の労働力不足を解消するために外国人材を受け入れる制度。
- 特定技能1号と2号の違い: 1号は基礎的技能、2号は熟練技能が必要で家族帯同も可能。
- 手続きの流れ: 労働契約締結から在留資格申請、支援計画書の提出までの明確なプロセスが必要。
- 必要書類と取得方法: 労働契約書や技能試験の合格証明書などを適切に用意することが重要。
- 雇用主の役割: 外国人労働者を円滑に受け入れるための支援体制と法令遵守が求められる。
この記事では、特定技能制度の基本情報や手続き、必要な書類について詳しく解説しました。
特定技能制度を活用すれば、深刻な人手不足に悩む企業も即戦力となる外国人材を確保することができます。
特定技能制度を利用する手続きが複雑と感じる場合には、信頼できる支援機関の協力を仰ぎましょう。
優れた外国人材を確保したいなら、ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関の『ミャンマー・ユニティ』にお申し付けください。
「ミャンマー・ユニティ」は、送り出し機関として、労働者選定から手続き、定着支援まで一貫してサポートします。
無料でご提供しております