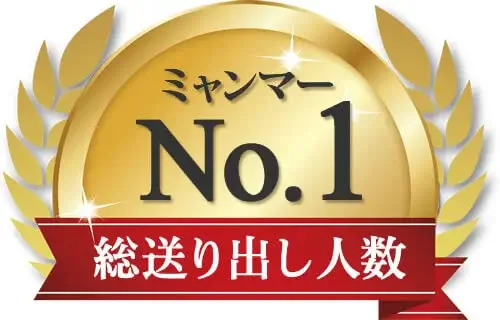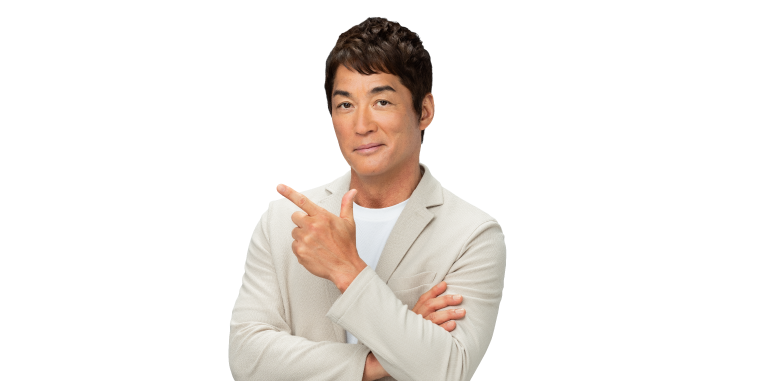技能実習生の現状と課題とは?失踪・低賃金・労働環境の問題を徹底解説!
技能実習生の受け入れを検討している企業の皆様の中には「思うように働かない」「トラブルが多い」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
技能実習生の失踪や長時間労働、賃金トラブルなど、制度上の課題は依然として多く、適切な対応が求められています。
しかし、正しい知識を持ち、適切な環境を整えることで、技能実習生の定着率を高め、企業の戦力として活躍してもらうことは十分に可能です。
この記事では、技能実習生の問題点とその解決策について詳しく解説しています。
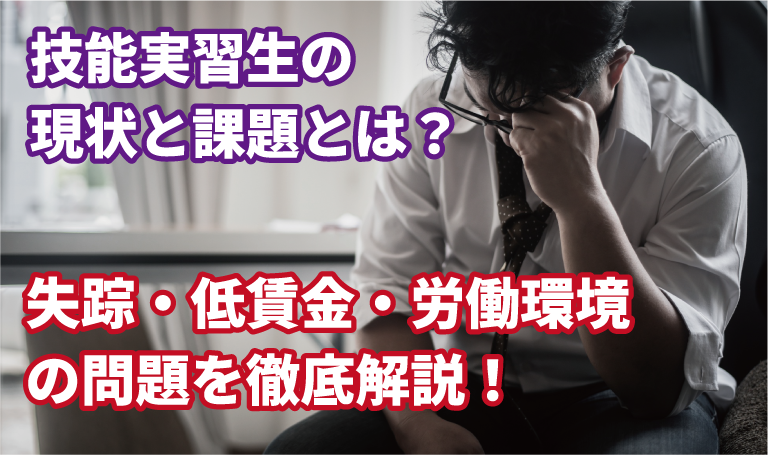
目次
技能実習制度の概要と目的をまず知ろう!
技能実習制度について5つのポイント
- 目的: 技能実習制度は、日本の技術や知識を発展途上国へ移転し、国際協力を推進することを目的としている。
- 対象者: 技能実習生は、母国で修得が困難な技能を習得するために来日し、企業と雇用関係を結んで働く。
- 在留期間: 技能実習生は、最大5年間、日本で実習を行うことが可能。
- 制度の仕組み: 企業単独型と団体監理型の2種類があり、約98%は団体監理型。
- 技能移行の仕組み: 実習は3段階(技能実習1号・2号・3号)に分かれ、試験に合格すると次の段階へ進むことができる。
技能実習制度は、日本の技術や知識を発展途上国に移転し、現地の経済発展を支援することを目的とした制度です。
この制度を利用し、外国人技能実習生は最大5年間、日本の企業で実習を行うことができます。
技能実習生は企業と雇用契約を結び、日本の労働法のもとで働きながら、技術や知識を習得します。
技能実習制度には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。
企業単独型は、日本企業が現地法人などの社員を直接受け入れる方式で団体監理型は、監理団体が技能実習生を受け入れ、日本の企業で実習を実施します。
また、技能実習は3段階に分かれており、技能検定試験に合格すると、1号(1年目)から2号(2〜3年目)さらに、実習実施者(受入れ企業)と監理団体の両方が優良認定を受けていれば3号(4〜5年目)へ進むことが可能です。
技能実習制度の目的と本来の趣旨とは?新しく始まった「育成就労制度」についても
技能実習制度は、1993年に「発展途上国への技術移転」を目的として創設されました。 日本の企業で技能を習得し、帰国後に母国の産業発展に貢献することが本来の目的です。
しかし、実態としては日本国内の人手不足を補う手段として利用されるようになり、本来の趣旨とは異なる運用が多く見られるようになりました。
技能実習生の労働環境に関する問題として、長時間労働や賃金未払いが指摘されています。
例えば、ある縫製工場では、技能実習生が毎月180時間を超える残業を強いられ、中には200時間を超える月もありました。
しかし、支払われた残業代は時給400円程度で、当時の徳島県の法定残業代時給849円の半分以下で、4年間で未払い賃金は200万円を超えていたそうです。
また、失踪した技能実習生の労働時間に関する調査では、最も多い労働時間帯が「40時間以下」で全体の40%を占め、50時間以下までで約80%に達しています。
労働時間が短いほど失踪者が多い傾向が見られ、これは技能実習生が十分な収入を得られないことが一因とされています。
これらの事例は、技能実習生が多額の借金を背負って来日し、過酷な労働環境や不当な賃金に直面している現状を示しています。
こうした問題を受け、日本政府は現在の技能実習制度を廃止し、2027年4月頃に「育成就労制度」を導入します。
この新制度では、以下の点が改善されます。
- 労働者の権利保護強化: 適正な賃金・労働環境の確保
- 転職の柔軟化: 一定条件のもと転職が可能
- 日本語能力とスキルの向上: 実践的な能力を持つ外国人を受け入れ
育成就労制度は、技能実習制度の問題点を解消し、より実践的な労働力確保を目的としています。
2025年3月に弊社が行った育成就労に関するセミナーは以下よりご覧いただけます。
企業側も、長期的な視点で外国人労働者を活用する新たな制度に適応することが求められます
技能実習生が直面する問題点の例とは?一部現在の技能実習生が直面する課題
| 問題 | 原因 |
|---|---|
| 低賃金 | 最低賃金ギリギリの給与設定や残業代未払いが発生。手数料や保証金の負担により実質賃金が低下。 |
| 長時間労働 | 慢性的な人手不足により、1日12時間以上の労働を強いられるケースが多発。適切な労務管理が行われていない。 |
| 劣悪な労働環境 | 高温・低温環境での作業や危険な作業を強いられる。保護具や安全対策が不十分な現場もある。 |
| 失踪問題 | 低賃金や厳しい労働環境、自由な転職ができない制度設計が原因。多額の借金を背負いながら来日し、より良い条件を求めて失踪するケースが増加。 |
| 人権侵害・ハラスメント | 言葉の壁や文化の違いにより、パワハラ・セクハラが発生。相談窓口が機能せず、問題解決が困難。 |
一部の技能実習生は、日本の労働環境の中で低賃金・長時間労働・劣悪な労働環境といった深刻な問題に直面しています。
厚生労働省の調査によると、技能実習生の平均月収は約15万円であり、これは日本人の平均月収と比較して大幅に低い水準です。
また、残業時間が月80時間を超えるケースや適切な労働管理が行われていない現場が多いことが指摘されています。
こうした問題を解決するためには、企業側の適切な労務管理と、技能実習生へのサポート体制の強化が不可欠です。
今後の制度改革により、技能実習生が適正な環境で働ける仕組み作りが求められています。
この章では、技能実習生が抱えている問題について1つずつ解説します。
出典②:令和6年度年次経済財政報告(第2章3節)
1. 低賃金の現状
- 技能実習生の月給は平均15万円前後で、日本人労働者と比較して低い水準となっている。
- 一部の技能実習生は手数料や保証金の負担により、実質的な賃金がさらに減少する状況にある。
- 残業代の未払いが発生し、最低賃金を下回るケースも報告されている。
技能実習生の給与は、最低賃金ギリギリで設定されているケースもあります。
2023年のデータでは、技能実習生の月収は平均15万円程度と報告され、日本人労働者の平均給与と比べて低い水準です。
また、一部の企業では、残業代が適切に支払われず、最低賃金を下回る報酬しか得られないケースも報告されています。
これらの問題により、技能実習生は日本での生活が困難になり、失踪や転職を考える大きな要因となっています。
企業は適正な賃金の支払いと公正な待遇を確保することが求められています。
2. 長時間労働の問題
- 技能実習生の労働時間は1日12時間を超えるケースもある。人手不足を補うために、休日なしの勤務を強いられる事例も報告されている。
- 労働基準法に違反するケースもあり、健康被害や精神的ストレスの原因となっている。
技能実習生は、受け入れ企業の慢性的な人手不足を補うため、長時間労働を強いられるケースが増えています。
1日12時間以上の労働が常態化し、休日もほとんど与えられない事例が報告されています。
厚生労働省の調査によると、技能実習生の約30%が月80時間以上の残業をしているとされ、過重労働による健康被害やストレスが大きな問題となっています。
3. 劣悪な労働環境
- 高温・低温環境での作業や危険な作業を強いられるケースがある。
- 保護具や安全対策が不十分な職場が存在し、事故や怪我のリスクが高い。
- 言葉の壁が原因で、安全指導が適切に行われていない現場もある。
技能実習生の労働環境は必ずしも安全とは言えません。
例えば、冷凍庫内での作業が続き、適切な防寒対策が施されていないケースが報告されています。
また、高所作業や危険な機械を扱う業務に従事しながらも、十分な安全教育が実施されていない問題が指摘されています。
さらに、日本語が不自由な技能実習生に対して、適切な安全指導が行われないことも事故の原因の一つです。
労働災害の防止のためには、安全管理の徹底と多言語対応の指導が必要です。
4. 人権侵害・ハラスメントの問題
- 言葉の壁や文化の違いにより、パワハラ・セクハラが発生している。
- 相談窓口が機能しておらず、技能実習生が問題を訴えられない状況が続いている。
- チェック体制が不十分で、問題が放置されるケースがある。
日本語の壁や文化の違いにより、職場でのパワハラ・セクハラに直面している問題も報告されています。
一部の工場では、日本人従業員からの暴言や暴力が問題となっており、適切な対応が行われていない事例も報告されていました。
さらに、技能実習生の多くは、相談窓口の存在を知らない、または信頼していないため、問題を訴えることができない状況があるようです。
中には監理団体のチェックが形骸化しているケースもあり、問題が放置される状況が続いています。
企業側は、技能実習生が安心して働ける職場環境を整備し、相談しやすい窓口の設置や、監査体制の強化を行うことが重要です。
さて、ミャンマー・ユニティでは、技能実習生の労働環境改善に向けたさまざまな対策を実施しています。
ミャンマー・ユニティが行っている技能実習生の労働環境改善対策
まず、低賃金の問題に対しては、受け入れ前の事前教育で給与計算や労働基準法の基本知識を指導し、技能実習生が適正な賃金を受け取れるようサポートしています。
- 長時間労働の抑制: 監理団体と連携し、労働時間を定期的にモニタリング。適切なシフト管理を推奨し、過重労働を防止。
- 劣悪な労働環境の改善: 入国前に安全管理教育を徹底。日本語講座を開設し、職場の意思疎通を円滑化。
- 失踪問題の防止:技能実習生に定期面談を実施。不安解消のサポートや企業向けの信頼関係構築研修を提供。
- 人権侵害・ハラスメント対策: 相談窓口を設置し、問題を報告しやすい体制を構築。企業と連携し、ハラスメント防止研修を実施。
長時間労働の抑制には、監理団体と連携し、技能実習生の労働時間を定期的にモニタリングする仕組みを導入。また企業に対して適切なシフト管理を推奨し、過重労働を防ぐ取り組みを行っています。
劣悪な労働環境の改善としては、技能実習生が安全な環境で働けるよう、入国前に作業の安全管理教育を徹底。
加えて、日本語能力の向上を目的とした講座を開設し、職場での意思疎通をスムーズにすることで安全対策の強化を図っています。
また、失踪問題の防止策として、技能実習生に対し、定期的な面談を実施し、悩みや不安を解消できる環境を整備し、企業側にも、技能実習生との信頼関係構築のための研修を提供しています。
そして、人権侵害やハラスメント対策として、相談窓口を設置し、技能実習生が安心して問題を報告できる体制を整えています。
これらの対策を通じて、ミャンマー・ユニティは技能実習生が安心して働ける環境づくりに努めています。
技能実習生をめぐる犯罪やトラブル事例とは? 犯罪に巻き込まれる技能実習生の実態
| 犯罪・トラブルの種類 | 具体的な問題 |
|---|---|
| 人身取引(労働搾取・性的搾取) |
|
| 詐欺・不法就労 |
|
| 暴力団や犯罪グループとの関与 |
|
日本に来た技能実習生の中には、犯罪に巻き込まれたり、搾取されるケースが後を絶ちません。
警察庁の報告によると、2023年には技能実習生に関する人身取引の事案が数十件発覚しており、その多くが低賃金労働の強要や性的搾取を目的としたものでした。
また、SNSを利用した投資詐欺や闇バイトの勧誘が急増しており、特にベトナム人技能実習生がターゲットとなる事例が報告されています。
他には不法就労を目的とした偽装雇用の斡旋、暴力団や犯罪組織が技能実習生をターゲットにし、違法な金融業務や薬物取引の運び屋として利用するケースも増えています。
近年増加傾向にある技能実習生の闇バイト問題
近年、日本人だけでなく、技能実習生においても「闇バイト」と呼ばれる違法な労働に関与するケースが増加しています。
その背景には、低賃金や過重労働による生活苦があり、SNSを通じて高収入を謳う違法な求人に引き込まれる技能実習生もいると報告されています。
2025年1月に北海道では、ある技能実習生がサケの密漁に関与した事件が発生しており、彼らは母国での借金返済のため、SNSで見つけた違法な仕事に手を染めたとされています。
また、警察庁の報告によれば、SNSを介して犯罪組織を形成する事例も確認されています。
さらに、円安や物価高騰の影響で、外国人労働者も手渡しの違法バイトに手を出すケースが増えており、Facebook上で情報をやり取りしているグループも存在しているとされています。
こういった状況は、技能実習生の労働環境や生活支援の改善が急務であることを示していると言っても過言ではないでしょう。
企業の経営者や意思決定者の皆様には、技能実習生が安心して働ける環境づくりと、適切なサポート体制の構築が求められています。
技能実習生の問題が発生する原因とは? 一筋縄ではいかない様々な問題
| 問題の種類 | 原因 | 詳細 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 文化・宗教の違いによるストレス | 技能実習生の適応問題 | 宗教・文化的背景と労働環境のギャップ | 社内研修の実施と異文化理解の促進 |
| 監理団体・送り出し機関の問題点 | 監理団体の機能不全 | 悪質な監理団体による搾取 | 公的な監理団体との連携強化 |
| 想定賃金と実質賃金のギャップ | 技能実習生の期待と現実の違い | 日本での生活費と給与のバランスが合わない | 生活支援の充実と適切な給与の確保 |
技能実習生が直面する問題の多くは、文化・宗教の違い、監理団体の問題、賃金のギャップなどに起因しています。
例えば、イスラム教徒の技能実習生は豚肉を避ける必要がありますが、食事の選択肢が限られる職場では大きなストレスとなります。
また、監理団体による適切なサポートが受けられず、技能実習生が孤立するケースも多数報告されています。
特に、送り出し機関による高額な手数料負担が問題視されており、技能実習生が多額の借金を背負って来日するケースが増えているようです。
こういった問題に対して、ミャンマー・ユニティでは、技能実習生が安全に渡航し、適正な労働環境で働けるようにするため、透明性のある募集体制と費用負担の軽減に取り組んでいます。
ミャンマー・ユニティが行っている技能実習生のトラブル対策
まず、ミャンマー・ユニティではブローカーを介さず、信頼できる日本語学校と連携をしたり、や求職者ネットワークを活用し、適正な選考を行っています。
ブローカーを介入させず、信頼できるネットワークから人材を集めているため、不当な手数料を課す悪質な業者の介入を防ぎ、技能実習生の経済的負担を軽減しています。
さらに、手数料以外の費用を徴収せず、負担を最小限に抑えた料金体系を採用しており、多額の借金を背負って来日するリスクを減らし、技能実習生が安心して働ける環境を整えています。
また、渡航前の教育においては、日本語学習だけでなく、日本の労働法や文化、職場のルールについても徹底指導を行い、技能実習生が円滑に適応できるようサポートしています。
こうした取り組みにより、技能実習生のトラブルを未然に防ぎ、安全で健全な実習環境の実現を目指しています。
【関連項目】ミャンマー・ユニティの強み1. 文化・宗教の違いによるストレス
問題の概要
- 具体的な問題: 宗教的な食事制限や礼拝時間が確保されず、技能実習生が強いストレスを感じる。
- 原因: 企業側の異文化理解が不足しており、適切な対応がなされていない。
- 解決策: 事前に宗教・文化を学ぶ研修を行い、企業内での配慮を促進する。
技能実習生の多くは、自国の文化や宗教的価値観を持ち、日本の労働環境に適応することが求められています。
しかし、宗教上の礼拝や食事制限への配慮が不足している企業も多く、技能実習生にとってストレスの要因となっています
例えば、イスラム教徒の技能実習生が多い職場では、ハラール食品の提供や礼拝スペースの確保が課題となります。
企業側がこの問題に適切に対応するためには、社内での異文化理解研修の実施や、マニュアルの整備が効果的です。
また、企業が積極的に技能実習生の意見を聞き、働きやすい環境を整えることが、定着率向上にも寄与します。
2. 送り出し機関の問題点
問題の概要
- 具体的な問題: 一部の悪質な送り出し機関監理団体が、技能実習生から不当な手数料を徴収し搾取している。
- 原因: 送り出し機関の審査が不十分で、違反が見逃されている。
- 解決策: 適正に業務を遂行している政府認定の送り出し機関との連携を強化し、透明性を確保する。
技能実習生の本人負担額については、それぞれの国においてその国独自の規定がございます。
しかし、一部の送り出し機関は、技能実習生から不当な手数料を徴収したり、利益を求めすぎるあまり、技能実習生の負担の部分が本人の人生にどのように影響するかをあまり考えていないケースも見受けられます。
解決策として、適正に業務を遂行している政府認定の送り出し機関との連携を強化し、透明性のある管理体制を整備することが重要です。
企業側も送り出し機関を選定する際に、実績や評判を確認し、技能実習生の権利が適切に守られる環境を確保する必要があります。
弊社ミャンマー・ユニティの大きな特長として、「本人の負担を最小にする」というモットーがあり、ミャンマーの政府が定めている「技能実習生から2,800ドルしか徴収してはならない」というルールを徹底して守っております。
なぜそんなことをするのかと言いますと、技能実習制度が廃止された原因にもなっている「本人負担が大きすぎる」ということを我々も問題視しているからです。「借金漬けとなって日本にやって来て追い込まれ、闇バイトのような悪の手に巻き込まれる」という最悪のシナリオを防ぐために、本人負担が増える三大要素となる「過剰な接待」「バックリベート」「ブローカー介入」を完全に排除しております。
この「本人負担を最小にする」取り組みはミャンマー国内でミャンマー人により大きく評価され、結果、ミャンマー・ユニティは2019年にミャンマーNo.1送り出し機関としてミャンマー政府から表彰されました。
そして現在、ミャンマー・ユニティにおいては技能実習生の失踪はほとんど発生しておりません。送り出し機関の問題点を根本から解決した稀有な例とも言えると思います。
3. 想定賃金と実質賃金のギャップ
問題の概要
- 具体的な問題: 聞いていた話と違うなど、想定していたよりも手取り額が低く、生活費の負担が大きいため、失踪リスクが高まる。
- 原因: 現地での入国前の説明不足により、技能実習生の期待と現実の間にギャップが生じている。
- 解決策: 事前に給与体系を詳しく説明し、生活支援を充実させる。
多くの技能実習生は、日本で高い収入を得ることを期待して来日します。
しかし、税金や生活費の負担が大きいため、実際の手取り額が期待よりも低いと感じるケースが少なくありません。
特に、家賃や交通費などの生活費が想定以上にかかっていたり、日本国内の物価が上昇していることもあり、技能実習生の経済的負担が近年増加し続けています。
この問題を解決するためには、事前に給与体系を詳しく説明し、生活支援を充実させることが重要になります。
例えば、住居手当の提供や、生活費の見積もりを渡航前に共有することで、技能実習生の期待と現実のギャップを減らすことができます。
技能実習制度の今後の展望と企業が考えるべき今後の対応策
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の見直しと育成就労制度の導入 |
|
| 賃金・労働環境の改善 |
|
| 監理体制の強化と企業責任の明確化 |
|
| 特定技能制度との統合的な運用 |
|
| 外国人労働者受け入れ政策の変化 |
|
技能実習制度は、今後「育成就労制度」へ移行します。
これは、従来の「技能移転」から「労働力確保」へと目的を転換し、より柔軟な受け入れを可能にする制度となる予定です。
また、技能実習生の賃金水準の引き上げや労働条件の改善が求められており、特に最低賃金の上昇が企業の雇用戦略に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、監理団体の役割強化により、不適切な実習環境を防ぐ制度改革が進み、企業のコンプライアンス遵守がより厳格に求められます。
今後は、特定技能制度との統合的な運用が促進され、実習終了後のキャリアパスが明確化されるでしょう。
少子高齢化に伴い、外国人労働者の受け入れ政策も転換期を迎えており、企業は柔軟な対応がこれまで以上に求められるようになります。
出典②:Works University 労働政策講義2024 17 外国人労働者
技能実習生が抱える様々な問題まとめ
理解してほしい5つのポイント
- 過度な借金問題:多くの技能実習生が費用と時間を費やして来日しています。
- 失踪の増加:劣悪な労働環境や賃金未払いが原因で、技能実習生の失踪が増えています。
- 労働環境の問題:長時間労働や安全対策の不備が指摘されています。
- 言語・文化の壁:日本語や日本の文化に対する理解不足が、職場でのコミュニケーション障害を引き起こしています。
- 管理監理体制の不備:監理団体や受け入れ企業の管理不足が、技能実習生の問題を深刻化させています。
この記事では、技能実習生が直面する主な問題点を取り上げました。
これらの課題を解決し、優れた外国人人材を確保するためには、信頼性の高い送り出し機関との連携が不可欠です。
ミャンマー政府認定圧倒的No.1送り出し機関の「ミャンマー・ユニティ」は、質の高い人材を日本企業へ送り出し、労働者選定から手続き、定着支援まで一貫したサポートを提供しています。
外国人雇用を検討されている企業様は、ぜひ「ミャンマー・ユニティ」へのお問い合わせをご検討ください。
ミャンマー・ユニティへのお問い合わせはこちら
▶ミャンマー・ユニティ公式サイト無料でご提供しております